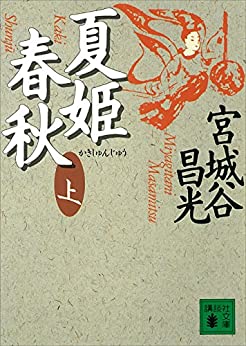覚書/感想/コメント
第105回直木三十五賞受賞作品
夏姫は「妖婦」、巫臣は「佞臣」のイメージがあった。夏姫は、かの女を撫有したものはつぎつぎ奇禍に遭う。恐ろしい女だというイメージがある。
そして巫臣については、主君を欺き、周囲の人間にあらぬ事を吹き込んで夏姫を手に入れたというイメージがある。全くもって悪いイメージしかなかった。
だが、本書ではこのイメージが覆った。
なるほど、夏姫は男どもを殺したわけではない。権力を貪ったわけでもない。偶然というか、たまたまというか、自分を撫有したものがつぎつぎと奇禍に遭っただけだ。かの女が手を下したわけでもない。
巫臣についてもそうだ。夏姫を手に入れただけだ。それも、奪い取ったわけではない。
夏姫を撫有したもので唯一奇禍にあわなかったのが巫臣である。とすると、この二人の出会いは必然であり、運命であるといえる。夏姫の伴侶は巫臣でなければならなかったのだ。
従来記述されてきたものが、悪く書かれているので、悪いイメージがつきまとったのだ。
絶世の美女で、権力志向が高くいと、悪女になる可能性が高いという。これに残忍性が加われば希代の悪女となる。
夏姫は絶世の美女であったが、権力志向はなかった。だが、周りには不幸がつきまとう。ある意味薄幸の美女ともいえる。
だが、あまりにも大きな不幸が続けざまに訪れると、なにやら見えないものが夏姫にあるとして、恐れ忌み嫌われたのであろう。
だから、こうした夏姫の不幸な面に新たな解釈を加えれば、本書のようになるのだろう。
ようは見方の問題である。
本書は、ある種淫靡な出だしで始まる。
だが、全編を通じてみると、妖艶な感じはない。むしろ、爽やかな感じすら受ける。
その大きな要因は、本書のキーワードとなっている「風」であろう。
本書で語られる「風」は様々な「風」である。激しいのもあれば、涼やかで爽やかなものもある。そうした風の中心にいるのが夏姫である。
物語の前半では、この「風」の意味が分からなかった。なぜ、ここまで度々この言葉を登場させるのか?意図が分からなかった。
だが、楚王・旅のもとに送られて、楚王が「風伯」が夏姫に宿っているかもしれないと考えるところで、すべてが理解できた。そして、この時点になって、はじめて前半のイメージというものが具体的にわき上がった。
最後に物語となる春秋時代について。
春秋時代は約三百二十年ある。
君主がそれぞれの国での最高権力者であり得たのは、初めの百年くらいだったようだ。
その後は各国の大臣たちに権力を握られる。だから、君主は大臣の任免を独断できない。
そして、各国の大臣たちは、主君との結びつきより、他国の人物との人脈に重きを置いていた時代でもある。
それゆえに、外交もかなり複雑なものとなっている。本書の舞台のひとつ鄭と陳は、その中でも最も複雑な外交を繰り広げた場所である。
もっとも、こうした権の降下現象は西方の秦と南方の楚ではみられない。
文化は周辺部で保持されるものであるらしい。
内容/あらすじ/ネタバレ
夏姫の生国は鄭である。父は蘭といい、鄭の君主となったので、夏姫は鄭の公女である。
鄭は交通の要衝であることから、貴人も庶民も人慣れし、いちはやく合理と進運が芽生えた国である。それゆえに文化の先進国ではあったが、倫理面に腐臭が漂うのも早かった。
十歳をすぎたばかりの夏姫が兄の子夷によって女の性を鑿開された。その後、たちまちに女の艶美が後宮の妃妾をしのぎ、大人の目を驚かすほどの魅力を溢れさせた。
この兄弟の不倫をかぎつけたのが子宋であった。かれの食指が動き、卿の子家とともにかの女の閨門を訪ねた。鄭室には淫欲の血がながれている。
夏姫についての好ましくない艶聞が蘭の耳に入った。他国に噂が広がる前に、嫁がせてしまおう。心当たりはある。
…この年の晩秋、鄭は楚の命令で軍旅を催した。この時に陳の国主・朔もきていた。蘭はこの陳の少西氏に嫁がせることにした。
少西氏は陳の公族のひとりであり、通常あざなの子夏から「夏氏」と呼ばれることが多い。鄭室の姓は「姫」である。嫁ぐのは子夏の息子・御叔である。
夏姫の婚約について血相を変えたのが兄の子夷であった。一方の御叔もこの婚姻には消極的であった。だが、それは夏姫を見るまでのことである。
子夏は夏姫をみて妖美すぎると不快に思った。そして、もしもこの女を見るすべてのものが魅せられるとすれば、我が家の不幸はこの女から始まるとも思った。
…この頃、北の晋と南の楚という強国に挟まれている、鄭と陳は難しい外交を迫られていた。そのため、二面外交といえる外交を採用する。そうした外交の中で、子夷は楚に向かうことになる。そして人質同然に楚に留まることになる。
夏姫と御叔との間に息子・徴舒が生まれた。あざなは子南である。
…大小の国の君主が病没した。楚の商臣などである。陳では平国が君主となっていた。
楚の喪中の中、子夷が楚を出発して鄭に戻ってきた。時期を同じくして夏姫の夫・御叔が死んだ。
鄭に戻った子夷は楚と結ぶべきだと考えていた。それは楚の新君主が聡明であること、対して晋の君主が暗君であると見極めたためである。
その楚王・旅が北上してきた。それは楚の威を示すためのものであり、攻略の色は薄かった。楚王・旅はわざと暗愚にみせ、臣下たちの様子をうかがっていた人物である。偽りの姿を脱ぎ捨てた旅は明君としての資質をあらわし始めていた。
その旅にとって、宋や陳を脅威にさらすことで晋がどのように動くのかが興味あった。
…蘭が死んだ。跡を継いだのは子夷だった。楚支持者の子夷は楚との同盟関係を強化する。だが、子宋、子家らによって誅殺されてしまう。
夫を亡くし、兄も亡くした夏姫の身分は不安定なものになっていた。住んでいる領地を取り上げられ、夏姫と徴舒は苦しい生活を余儀なくされる。こうした生活の中、徴舒は元服して子南と名乗る。
夏姫はここに一つの覚悟をした。その結果、夏氏の領地は保障され、子南の将来も約束された。夏姫の覚悟は自分の身体を平国や儀行父、孔寧に与えることであった。だが、このことが子南を苦しめ、大きな決意を胸に懐かせることになる。
…夏姫は楚へ連れて行かれた。楚王・旅は夏姫の体内に風伯を宿しているらしいと推測していた。それは子南の叛乱によって楚に逃げ込んでいた儀行父の言葉によってそう思っていたからである。
だが、夏姫の風伯が楚にとって吉なのか凶なのか分からなかった。それゆえに手を出せないでいる。そのことを巫臣に訪ねた。巫臣は夏姫をみた。そして、凶であると告げた。
巫臣は夏姫をみて夏姫を幸せに出来る男はこの世で自分しかいないと直感していた。
本書について
宮城谷昌光
夏姫春秋
講談社文庫 計約570頁
春秋時代 紀元前7世紀
目次
艶蕾の章
春風の章
往来の章
月光の章
妖光の章
雪天の章
暗流の章
南風の章
樹響の章
武神の章
新古の章
凶風の章
落葉の章
宿星の章
落日の章
孤独の章
生死の章
弓矢の章
来復の章
女流の章
明暗の章
幻影の章
会戦の章
覇者の章
再会の章
脱出の章
風神の章
あとがき
登場人物
夏姫
<鄭>
蘭…夏姫の父
子夷…夏姫の兄
子宋…公族出の大臣
子家…卿(首相)
<楚>
商臣(穆王)…楚王
旅(荘王)…楚王
樊姫…旅の王妃
伍挙
巫臣
<陳>
朔(共王)…国主
平国…国主
儀行父
孔寧
子夏…御叔の父
御叔…夏姫の夫
徴舒(子南)…御叔と夏姫の息子
季暢
<晋>
趙盾…大臣
士会…正卿