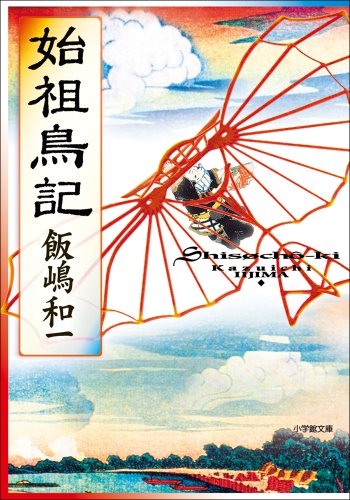第六回中山義秀文学賞受賞作品です。
“鳥人”といわれた備前屋幸吉の生涯を描いた歴史小説。
物語は備前屋幸吉から始まりますので、主人公は幸吉と思いがちですが、中盤は巴屋伊兵衛、福部屋源太郎らが主人公であり、そのほかにも後半には三階屋仁右衛門が重要な人物として登場します。
ですから、”主人公は一人”という固定観念で読まない方がよい作品です。
最初の十数ページを読んで、気軽に読むのをやめました。そうして読むには失礼な気がしたのです。久々に襟を正して、一ページ一ページを丹念に読むことに決めた作品でした。
私は本書を平成の歴史小説の中でも、指折りの傑作だと思います。また、歴史小説の枠を超えて傑作といえる作品だと思っています。
エンターテインメントを追求したい人や、軽めの何も考えなくていい小説を読みたいというのであれば、本書はお薦めしません。
初夏の瀬戸内海に吹く海風、潮騒が耳に鳴り響く。そうした穏やかな風景が、本書を読んでいるあいだ、ずっと頭をよぎっていました。
その淡々と綴られる文章とは裏腹に、心の奥底に潜むいいようのない怒りが横たわっているのを、物語の最初から感じました。
淡々と語られる文章は、いいようのない怒りを抑え込むために取った手法なのではないかと思ったくらいです。
このいいようのない怒りを、衝動、情熱、執着、固執などのように別の感情で捉えた人もいるでしょうが、私はどうしてもそういう風には捉えられませんでした。
物語で度々出てくるこうした言葉も、私の考えをそういう思いに向けたのです。
「サルどもは己というものがない。したがって他人の同意を何より欲しがる。絵や書の良し悪しなど初めから解しえないのだから、…(中略)…サルどもが競って買い集めてくるそんな書や画は、当然なんの面白みもない駄作ばかりだった。」
「古来怪鳥の噂は、必ずその時々の権力に対する民の非難として立ち現れる。かの源三位頼政が二度に渡って退治した鵺はいうまでもなく、南北朝の騒乱の中、隠岐次郎左衛門が紫宸殿で射殺した怪鳥も、腐敗しきった支配権力の滅亡を願う民の思いの化身に他ならなかった。」
こうした文章は、作者は明確な政治批判を含んだ文章に発展し、現在の状況に上手く当てはめることが出来るという意図のあるプロットに落とし込まれているように思われます。
最初は備前岡山・池田藩。池田藩が様々な口実を言おうとも、民の暮らしを困窮に追いやった原因のすべては、藩役人の無能腐敗と、それにつけ込んだ大商人の株仲間による商活動の独占にある、といった内容。そして天明三年の大飢饉の様子を、巴屋伊兵衛と福部屋源太郎の口を借りて語る場面など。
こうしたいいようのない怒りだけが、物語を支配しているわけではありません。
これを乗り越える力の象徴として幸吉を登場させ、そして巴屋伊兵衛、福部屋源太郎、杢平などの人物達に新たな力を与えています。
最後に、この乗り越える力が幸吉に還流されているところも構成が緻密です。
この他にも、登場人物に一種の共通性を与えているようです。
それは富田清兵衛の「その方の身の内にも、…風羅坊が住むか」という言葉です。
“風羅坊”については物語の中で語られているので、そちらで確認頂きたいのですが、登場人物達には一様にこの”風羅坊”が住み着いているのではないか。私はそう思いました。
最後に、中盤の主人公、明けて二十六で亡くなった巴屋伊兵衛の物語には涙を流さずにはいられませんでした。
凄い一冊でした。
内容/あらすじ/ネタバレ
―天明五年(一七八五)、備前岡山
未明に紙屋藤助の家を同心らが取り囲んだ。城下では空を自由に飛び回る鵺が一帯を騒がせていた。源三位頼政が射止めた怪鳥鵺と同じく「イツマデ、イツマデ」と鳴いては藩の失政をあざ嗤い続けていた。その居場所を突き止めたのだ。
紙屋には主の藤助の甥に当たる兄弟が身を寄せていた。兄弟は児島生まれで、当年数え年二十九と二十七になるはずだった。兄が号を周吾、本名を幸吉、弟は弥作といった。
幼い頃から幸吉には非凡な才能があった。それは絵に現れ、それに気がついたのは旅回りの砂絵師だった。そして、幸吉には鳥寄せに長け、雀や鶺鴒、頬白などを手の平にのせることが出来るという不思議な能力を持っていた。
幸吉は叔父に当たる傘屋萬蔵の元に引き取られていた。父瀬兵衛が死んだためだ。弟弥作も児島湾を隔てた岡山の母親の実家である紙屋に養子に出されていた。
傘屋で住み暮らすようになって、竹や紙、糸などが自由に手に入るようになると、幸吉は様々な凧を作ることに没頭した。
そして、あることがきっかけで、岡山の藤助は幸吉を自分の所に呼び寄せることにした。
幸吉と弥作の兄弟は紙屋でめきめきと腕を上げ、表具師としての評価も高まっていた。幸吉は世俗の金銭価値でしか物事をはかれない輩を毛嫌いしていた。書画の意匠にかかわらず、金糸や銀糸の絢爛たる裂地をふんだんに使いさえすれば喜ぶような輩だ。幸吉はこうした輩を「あのサルが…」でみな片づけてしまう。
やがて、得体の知れない河童らしきものが闇夜京橋に出没するとの噂が、岡山城下に飛び交うようになった。
幸吉の凧熱はさらに高まっていた。この頃には自分が凧にぶら下がって空に飛ぶことを繰り返し試し始めていた。これがやがては鵺騒ぎへと発展していく。
―天明五年(一七八五)、下総行徳
地廻り塩問屋の巴屋伊兵衛は、暗澹たる思いで、遺体を見ていた。二年前の天明三年は悪夢の年だった。北の諸藩では数十万といわれる未曾有の死者を出した。だが、この死んだのは民百姓ばかりだった。藩士の家で餓死したものなど一人としていない。民を顧みない糞侍の悪政の結末に他ならない。
江戸の下り塩問屋でも、たった四軒が莫大な下り塩を独占しており、民の生活を握っていた。行徳ではこれに対抗するすべを失いただひたすら自滅していくのを待っているだけだった。巴屋伊兵衛が見つめる遺体と同じような人間がこの行徳にも出るのは時間の問題である。
伊兵衛には一つの算段があった。そのために上方に上り下り塩を行徳まで運んでくれる廻船問屋を探す必要がある。だが、上方に来て江戸四軒問屋が廻船問屋にまで力が及んでいるのを知る。失意の中で知り合ったのが福部屋源太郎と、その楫取・杢平だった。
廻船業でも伊兵衛の塩問屋と同じ問題が持ち上がっていた。公儀の認めた商いのみに縛られ、それ以外の身動きはとれない仕組みとなっていた。海は糞侍どもの糞尿のためにすっかりけがされた。源太郎はそう感じていた。
二年前の大飢饉が糞侍の暮らしを守るためのばかげた仕組みによるものであることは、廻船業に携わるものなら誰でも知っている。三人に一人が餓死したという津軽藩が、四十万俵を超える米を大坂や江戸に送っていた。源太郎はそれを見ていた。そして、その俵は彼の地で飢えのために果てた死体が山積みになっているものにしか写らなかった。
源太郎の耳に、岡山の鵺騒ぎが入ってきた。その空を飛んで世間を騒がせたのは、源太郎の知っている幸吉だった。
気がつくとため息ばかりついている。幸吉の噂を十六年ぶりに聞いて、源太郎は目が覚める思いだった。おれはこんなところで、いったい何をやっているんだと、無性に己に腹が立ってきた。おれは江戸の問屋たち、ひいては公儀とぶつかるのを逃げていた、やっと踏ん切りがついた。塩問屋の巴屋伊兵衛と知り合ったのは天啓だ。巴屋伊兵衛の所に塩を運ぼう。そう腹をくくった。
―寛政十年(一七九八)駿河府中
備前屋幸吉は木綿問屋を営んでいた。町頭の三階屋仁右衛門は備前にゆかりのある人間だろうという程度にしか思っていなかった。関わりが出来たのは、自分の所有する斗圭(時計)を修理してもらってからである。
そして親しくなってから、仁右衛門は幸吉に凧を作ってくれないかと頼み込んだ。端午の節句で揚げる凧である。仁右衛門は幸吉の前身を知らなかったのだ。
幸吉は己の中で強いて忘れようとしていたものが、起きあがってくるのを感じた…。
本書について
飯嶋和一
「始祖鳥記」
小学館文庫 約五〇五頁
江戸時代 備前屋幸吉
目次
第一部
第二部
第三部
登場人物
幸吉(備前屋幸吉、周吾)
弥作…幸吉の実弟
藤助…紙屋主
ミヲ
瀬兵衛…桜屋主、幸吉の実兄
幸助…瀬兵衛の息子
<下総行徳>
巴屋伊兵衛…地廻り塩問屋
<廻船業>
福部屋(平岡)源太郎
杢平…楫取
平吉
矢野兵左衛門…尾州知多廻船講世話人
<備前岡山藩>
富田清兵衛…町目付
横山左門…同心
喜八郎…名主
理右衛門…五人組頭
卯之助…砂絵師
おキヌ…茶屋女
<駿河府中>
三階屋仁(甚)右衛門…町頭
ウタ