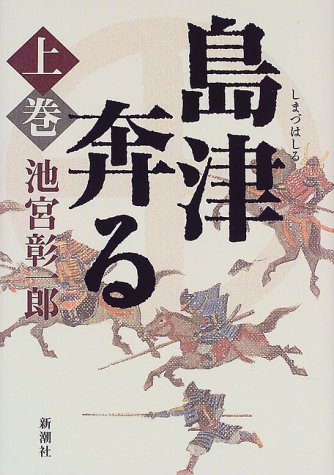第12回柴田錬三郎賞
薩摩・島津家を通して見た関ヶ原です。
最後の「補遺」で描かれる中馬大蔵の逸話が、薩摩が経験した関ヶ原の大変さを能弁に語っています。
「さても、関ヶ原と申すは…」
三度絶句して、言葉の出ない中馬大蔵の脳裏に浮かぶのは、七年にわたる地獄の朝鮮の役であり、関ヶ原での退却戦であり、主君義弘の面影でした。
本書で描かれる全ての出来事が、この中馬大蔵の三度の絶句の中に込められており、稀に見る名場面となっています。
この中馬大蔵に関しては海音寺潮五郎氏も同じ逸話を「男一代の記」((「かぶき大名」収録)で描いています。
本書は慶長の役の撤退戦から描かれ始めます。
主人公となるのは島津家の当主・島津義弘。流動的な政治情勢の中で、徳川家康と敵対したにもかかわらず領土を失わないように苦心した姿を描いています。
義弘が敵対した徳川家康は小心者として描かれています。
義弘の兄で前当主だった島津義久は器の小さくなった保身に走る人物として描かれており、保身に走りすぎて、何もしない人物として書かれています。
そうした人物に対しては池宮彰一郎氏はこう批判しています。
『為さざるは罪なしというのは常人のことだ。かりそめにも人の上に立つ者は、誤りを見逃し見過ごせば、それのみで悪である。それが職務・責務というものだ』
石田三成についてもバッサリと斬り捨てています。石田三成を斬り捨てているというよりは、「吏僚」「官僚」というものを斬り捨てています。石田三成は「吏僚」「官僚」の代表というわけです。
石田三成は吏僚的な思考に陥り、おのれを過信し、錯覚しました。国政の中枢業務を管掌していると、おれが国を動かしていると錯覚するのです。
『吏僚、という化物は、常人ではない。人外と思っていい。自分の処理・処断がどのような迷惑を生じ、時には生活破綻を来すような悲劇となっても、一切関知しようとせず、感情を動かすことをしない。-(中略)-
ゆえに彼らを人と思ってはいけない。彼らは民から見たら化け物である。』
この石田三成の指金で朝鮮出兵が始まったというのは興味深い見解です。
天下争乱がおさまったら、戦後不況が起きます。軍兵将士の人余という失業者がでます。何せ、百二十年余続いた戦争景気が終焉するのですから。
官僚の三成が考えたのは、いわば植民地獲得です。戦争している間は戦争景気を煽り、獲得した財貨で景気を沈静化させます。
内容/あらすじ/ネタバレ
慶長三年(一五九八)、陰暦九月初旬。朝鮮半島の泗川新城に島津義弘はいた。兄義久が領主の座を退き、今は義弘が領主である。
甥の島津豊久が早船でやってきたと長寿院盛淳が伝えてきた。豊久は義久・義弘の末弟・家久の子である。
豊臣秀吉が死んだという。そして帰国せよとの命であった。だが、この負け戦の中では至難の業だ。
明・朝鮮軍の兵力は二十万を超えている。薩摩の兵力は六千を超えるくらいである。そして義弘が顔色を変えたのは、国許からの援軍が全く期待できないと聞いたからだった。
義弘は薩摩の生き残りのため、そして他の日本軍が生き残るための必勝の作戦を考えていた。そのために選んだ作戦が「釣り野伏せ」であった。島津は国内においても鉄砲の保有は群を抜いていた。そして御家芸である乱射がある。
義弘の作戦がはまり、明・朝鮮軍は文字通り壊滅した。わずか七千の手勢で三十倍の二十万を完膚なきまでに打ち破った。島津家の退却の路は確保された。義弘は「石曼子(シーマンズ)」と恐れられた。そして、朝鮮水軍の李舜臣をも撃破し、敵を畏怖せしめた。
朝鮮からの撤退戦で義弘は近くの立花勢などの援軍を頼まなかった。理由がある。天下は豊臣秀吉の死によって動くと義弘は読んでいた。薩摩は南の果て、地の利なく、戦力不足、財力不足だ。薩摩は強悍の威名が知れ渡れば、薩摩勢には容易に手を出さないだろう。薩摩島津の家名と領国を争いの埒外に置くには必要なことだったのだ。
帰国そうそう、義弘を悩ませる問題がある。次の天下は誰か。これを知るのが愁眉の急である。でなければ四百年間続いた薩摩島津家は滅びる。上方では徳川家康と石田三成の確執が深刻化している。義弘は天下の情勢、他家の内情を知るために、諜報網をととのえることにした。
もう一つの悩みがあった。それは宿老の伊集院忠棟のことである。
島津の政治は二頭政治だといわれる。現領主の義弘は外交と軍事を専断し、二つ上の兄で前領主の義久(龍伯)は家と国の内政を司っている。
上方で徳川家康と相談をしていた本多正信は、義久と会った時のことを思いだしていた。器が小さくなった。そして、義久は義弘に嫉妬しているのではないかと考えた。
義弘は薩・隅二州の太守として激動の時代を乗り越えるために知能の限りを尽くしているが、兄・龍伯は我が身の安逸のみを願う一介の老爺となっていた。
義弘は六十五歳になっている。十年間、九州制覇に明け暮れ、そして地獄の朝鮮の役が七年続いた。その間に、国は疲弊しきっていた。
京都伏見では愚劣で陰険な紛争が起きている。種を蒔いているのは本多正信だ。
徳川家康のところに問罪使がやってきた。無断で縁組みをしたことが問題になっているのだ。だが、家康はこれをかわしてしまう。
合戦の噂が流れ始めるが、島津家では平常と変わらぬたたずまいを保っていた。その中、世子忠常は伊集院忠棟を呼び、越権を理由に斬り捨てた。これが約一年続く荘内の乱を呼び寄せることになる。
義弘は忠恒に兵をつけ帰国させた。乱を討伐させるためである。入れ替わりに甥の豊久が上洛してきた。
徳川家康から、石田三成からも薩摩に接触があった。互いの陣営に組み込もうとしている。その中、前田利家が死んだ。
家康は次々に手を打った。そうした中で、石田三成は佐和山に追いやられ、前田家征伐の話が持ち上がる。
今、義弘の手元の兵力は増減が激しいが、二百から八百くらいの間を上下している。国許では士卒の帰国を命じ、義弘の増兵要求を聞いた外城地頭は手持ちの士卒を三十、五十と送り込む。確定的な兵力を持てないことを義弘は恐れた。時流は刻々にはやさを増している。
前田家が全面降伏した。次は上杉である。
義弘は豊久の前で組むならツキのある者を選ぶといった。天運は徳川家康にあるようだ。上杉討伐を前に、義弘は家康に賭けることにした。
そして、義弘は留守になる伏見城を守ると家康に約束した。これは家康が直臣の猛烈な反対にあい流れてしまう。結局、島津は伏見城へはいることはなかった。
薩摩では島津義久が中立を保つつもりでいた。
石田三成は徳川家康が上杉討伐に出ている時を狙って兵を挙げるつもりである。それを聞いた大谷吉継は止めたが、三成の気持ちを変えることができなかった。
三成は関所をつくり、東下する諸将や密使らが家康のところへ行くのを阻止した。そのため鍋島勝茂などが引き返す羽目になる。
大坂に集結した諸将は三十六名、九万を超える兵数だった。総大将は毛利輝元となった。これが家康の耳に届き、震えは止まらなかった。
義弘は薩摩へ書状を送った。それを受け取った長寿院盛淳はためらうことなく出陣の支度に取りかかった。無断の出陣だ。そして盛淳は主命に依らぬ志願兵を呼びかけた。
薩摩は兵農一致が続いている。中馬大蔵も畑で汗を流していた。すると、具足櫃を背負ったのが三人五人と肥後へ走っていく。中馬大蔵もとるものもとらず駆けだした。
上方へ。上方へ、一刻も早く上方へ。殿様の難儀である。突っ走れ。
島津家中、上方へ罷り通る。この一語は、通行手形のごとき効果を上げた。
島津勢は走った。
慶長五年、上杉討伐軍が一路西を目指した。そして石田三成も美濃へと出立した。島津家にも参陣要求が来た。
不本意ながらも石田方につくことになった義弘は、今頃も走っている島津勢をぎりぎりまで待つことにした。そして千余の兵を率いて美濃へ向かった。
西軍は十万の兵を持ちながら、戦の素人である。宇喜多秀家が到着した際に進言した夜襲を石田三成は却下したり、途中佐和山城へもどるなど混迷する。
各個ばらばらで動いている戦の中で、義弘はどうやって勝か、どうやって負けるかという難しい問題を抱えていた。
関ヶ原の合戦が始まった。最初の四時間は西軍が常に優勢だった。だが、一旦崩れるとわずか一時間で壊滅状態となった。
この間に島津の兵力は八百に減少していた。東軍は島津を遠巻きに見ていた。どうするのか。
島津は義弘を薩摩に帰すための最後の戦を仕掛けることにした。そのため、徳川家康の本陣の前を突っ切る。決死の士卒は先鋭な鏃の形に陣営を組んだ。島津兵は死兵と化した。
本書について
目次
玄鳥帰
海峡万里
遠慮近憂
腥風崩雲
狼子野心
同床異夢
以火救火
星火燎原
円鑿方柄
天道是邪非邪
婑子看戯
修羅八荒
死灰復燃
遊刃有余地
登場人物
島津義弘(惟新)
長寿院盛淳
島津豊久
新納旅庵
中馬大蔵…義弘の旗本
小芳…中馬大蔵の女房
棚辺屋道與…唐物商人
塩屋孫右衛門…廻船屋
山田有栄
島津義久(龍伯)
島津忠恒(家久)…義弘の三男、島津家の嗣子
伊集院忠棟
石田三成
島左近
舞兵庫
蒲生郷舎
大谷吉継
佐竹義宣
宇喜多秀家
立花宗茂
毛利輝元
吉川広家
安国寺恵瓊
小早川秀秋
松野主馬
福島正則
黒田長政
後藤又兵衛基次
徳川家康
本多正信
本多忠勝
井伊直政
榊原康政
渡辺半蔵