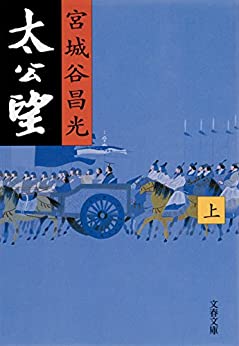覚書/感想/コメント
呂尚。別名は太公望。日本では釣り好きを指して太公望といいます。
言い伝えでは、渭水で釣りをしていた呂尚を文王が「これぞわが太公が待ち望んでいた人物である」と言って召し抱えたとされます。
実態は、謎に包まれた人物です。なにせ、中国がまだ神の時代、伝説の時代の人物だから、わからないことが多いのです。
望(=呂尚)は兵法家の祖といわれるように軍略に精通していました。
彼が名を成したのは、神を信仰した時代において、合理性を追求したからかもしれません。この物語を読めばそう感じるようになるでしょう。
さて、舞台は「商」の時代です。
世界史を学んだことがある人ならば、殷で知られる時代です。「夏」→「殷(=商)」→「周」へと移っていく時代が舞台です。
「商」民族は太陽信仰であり、太陽は10個あると考えていました。「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」です。
ちなみに「商人」といいますが、この「商」からきています。
太公望といえば有名なことわざがあります。「覆水、盆に返らず」
太公望が周に仕官する前、女と結婚しましたが、仕事もせずに本ばかり読んでいたので離縁されました。
のちに、太公望が斉に封ぜられるようになると、女は復縁を申し出たが、望は盆の上に水の入った器の水を床にこぼして、「この水を盆の上に戻してみよ。」と言います。
女はやってみたが当然出来ません。「一度こぼれた水は二度と盆の上に戻る事は無い。それと同じように私とお前との間も元に戻る事はありえないのだ。」と復縁を断ったそうです。
本当は、漢の朱買臣の逸話を換骨奪胎したといわれているように、まったくの作り話らしいです。
というのも、望の時代、本がありませんでした。何よりも、盆がなかったというのが真相のようです。
本作は作者にとって、特別の意味合いを持つ作品です。
作者には太公望を扱った小説が二作あります。「王家の風日」「甘棠の人」(「俠骨記」収録)です。
前作が処女作で、後が三作目です。作者は商(殷)周革命から中国史に入って作家となったのです。
商周革命を扱ったのは、この革命こそが中国史の原点であると思われたからだそうだ。そして、二つの小説を書き終えたあと、商王朝は太公望一人に倒されたという感想を持ったのだといいます。
だからこそ、太公望を正面から書かなければ、商周革命を書き尽くしたとはいえません。
そして書かれたのが本作でした。
つまり、「王家の風日」「甘棠の人」「太公望」のすべてを読んでこそ、宮城谷商周革命記は終了することになります。
登場人物の一人に妲己がいます。九尾の狐の伝説に結び付けられており、日本では九尾の狐の伝説に加えて玉藻前の伝説に繋がっています。
内容/あらすじ/ネタバレ
望は、泣けない、という哀しみがあることを知った。
この少年の中に、商王を殺すという復讐の炎が立ち、ついに消えなかった…。
この年、商王「帝乙」が崩御している。この死んだ王の従者が必要と考えられ、そのために異民族が殺された。
この「帝乙」の跡を継ごうとしているのが「受」であり、後に「紂王」と呼ばれることになる。
受の下には叔父の箕子と親友で部下である祖伊がいる。他に神速の飛廉がいる。
望は羌族に生まれた。羌族は大勢力を作ろうとしない。もしそうすれば商帝国となんら遜色のない勢力になれた。
だが、彼らには平等の思想があり、身分の上下の考えが薄く、強力な指導者が育たない。侵略の概念もなく、結果として戦闘力は低かった。
望はのちに「呂望」と呼ばれる。
望の一族が襲われ、望を含め六人の子供が生き残った。
彪、班、呉、詠、継が望のそばにいる。この六人がのちに斉という国を建て、呂氏の繁栄の基を築くことになる。
望は皆を連れて北の弧竹という邑を目指した。
望は黄金の喬木を目にしていた。
木の下には鳥の羽をつづり合わせた衣をまとった女がおり、呪文を唱えている…。
望には自然界の霊徳をうけいれたくわえる稟質がそなわっていたのだろう。
旰と名乗る男に出会った。羌族だという。なるほど男は辮髪をしている。
この羌族は羊の代わりに馬を飼っていた。それに族の大きさに驚いた。舎が5百はあるだろう、およそ二千五百人以上がいることになる。多馬羌と呼ばれる族である。
そして、この族には身分があるらしい。旰の下に仍と呼ばれる男がおり、仍の下に員という部下がいる。
この族での自分たちに対する扱いに望は疑問を持った。ある日、望は皆を連れて逃げ出した。六人は危うく商に差し出されるところだったのだ。
望は常人では打破できない苦難にかずしれず遭遇することになるが、幸運にも助けられ長寿を全うする男である。その奇蹟に満ちた生涯の一端が始まる。
望の前に現れたのは鬼方の主だった。
鬼公は望が心機に優れた少年であることを見抜いた。そして、望たちを迎え入れた。
鬼方は西北の大族で、東北の大族の土方に匹敵する勢力を持っている。鬼公はそこの王にあたる人物であり、それに望は見込まれたのである。望はたちどころに鬼公を尊敬した。
望は彪に弧竹に行くことを忘れたのかと聞かれた。父母を商に殺されたことは忘れない。だが、羌族だけでは戦えない。
望は、ここに商に対抗しうる勢力があることを知った。
鬼方と土方が接するあたりに箕邑がある。三十年以上も前に出現した邑だ。商の宰相というべき箕子の食邑である。
その箕邑から兵が出て鬼公を襲おうとしている。あちこちの異民族もそれに応じているという。凶報だった。
そして、箕子の使者が現れ、鬼公に土公に会わないかという。この使者は箕子本人だった。鬼公を窮地に立たせたのが箕子であれば、その窮地から救おうとしているのも箕子である。箕子に翻弄されたのだ。
土公がやってきた。
はからずも望はこの時代を代表する三英傑を目前することになる。
会見の中で、九夷、周をはじめとして異民族が続々と商に入朝するということが判った。
望は鬼公が眠っている間に土公と話をしたようだ。土公に弧竹へ連れて行ってもらう事になった。
望は鬼公に誓った。弧竹から戻ることがあれば、たとえ鬼公が商王の臣となっていても仕えると。
望は鬼公と別れる前に、ひとつ訴願した。
鬼方が馬羌を急襲した時に、捕虜を得た。その中に員がいることを知った。望は員を頂けないだろうかと願ったのだ。
員は馬羌には戻らないという。そのかわりに望の近くにいるという。だが、何か秘めたものを持っているようであった。望はあえてそれ以上を問わなかった。
弧竹には何があるのか。望は斿にたずねた。そこには山岳の神を祀るものがいるという。神は伯夷と呼ばれているという。
弧竹につき、望たちは熹に案内された。父と別れてから一年がたっていた。その間にあったことが頭をよぎった。死にかけたこともある。だが、自分も無事で、五人の子も無事であった。
弧竹は二本の柱が立ってる門だけがあった。
望は山に招かれた。老人が招いたのだ。
老人は望に剣を見せた。そして剣を学ぶために二載半を洞窟で過ごすことになった。そして、次に学んだのは文字であった。
望は十九歳となった。班が十五歳となっている。望は大きく成長していた。
望が留守の間に彪と呉、詠がいなくなってしまっていた。
そして、二十歳になったとき、弧竹をあとにするときがきた。
望が鄭凡と出会った。
鄭凡は望に商の新しい町である新邑を見に行かないかと誘った。
鄭凡は道々で望に、鋸橋と呼ばれる巨大な倉のこと、貨幣のことを説明した。
受王が即位して六年目になっていた。
望に男児が生まれた。伋と命名した。
望は商王朝を倒すために新邑にいくと逢尊に打ち明けた。鬼公は必ず商王から離れるはずである。そのとき、羌族に力を貸してくれるはずである。革命が成功すれば、鬼公が王になる。
逢尊は望が王になれという。庶民から王位についたものがかつている。たったひとりだ。名を舜という。東方の出身であり、商の高祖である。
望は東方を調べるために出かけた。逢尊は青年をつけた。咺という。奴隷である。春が終わるころ、望の配下は二人になった。牙という童子が仕えるようになった。
秋になること、妻の逢青が女児を生んだが、逢青が亡くなってしまった。望は呆然とし、そして泣いた。
鄭北で別れた後、ゆくえのわからなくなっていた員が望の前に立っていた。
仍を襲ったが、逆に殺されそうになったのだという。
員の話から商王朝がすべてがうまくいっているわけではないらしいということが判った。人方という異民族が、頑強に抵抗しているのだという。
鬼公が三公の位についたという。
代わりに九公がおとされた、九公の娘に仕えている継が心配である。商王と九公との間に何があったのか…。
望が見た新邑は竣工したばかりである。
政治の中心はここに移された。受王もここにいることになるが、このときは不在だった。
討伐の途中で一人の美女を手に入れていた。名を「妲己」といった。
望は鬼公を訪ねた。猶子の子良が出てきて望を打擲した。
望はこのたびのことで羌族は鬼方と組むべきではないことを教わった。
商と戦って勝った族がいる。周がそうである。もうひとつ、周と同じく西方にあるのだが、召という。
周公を中心にして商王の力政に反対する勢力が結集する気配がある。この話を望にしたのが周公の子、のちの周公旦である。小子旦は望に挙兵を知ったら親友を混乱させる手を打ってくれないかと頼んできた。
さきに立たず、さきに攻めず、さきに勝たず。それが全てである。望は子旦のために周に献策した。
三公が商王朝打倒の兵をあげても、周公には静観してもらう。中華が乱れに乱れてから腰を上げても遅くはない。
継を助け出すために望は動き始めた。
その過程で、有蘇氏の公女に会った。この公女こそやがて王朝の命運を左右することになる。妲己である。
望が蘇侯をしのぐ器量の大きさを持っていることに最初に気付いたのは盲目の史官の磊老であったかもしれない。
磊老は心の目で人物を見るが、その目に収まらないのが望の像であった。
磊老は望に故事を語っていた。帝舜からはじまり、望には生まれて初めて聞く話である。そして、血胤によって王が定められたのではない事実が太古にあった。舜と禹には血のつながりはない。だが禹は王位についた。
人が人を決める。鬼神や上帝が決めるわけではない。商王のもとから諸侯が去れば商王朝は崩壊する。そのことがわかった。
講和は三回で終わった。
その最後で磊老は伊尹の名を出した。夏王朝を滅ぼし、商王朝を興した本当の人物だという。
その名が出たとき、一瞬であるが室内に清澄の気が立ったように望には感じた。
伊尹とは何者か。伊尹は自分にかかわりがあると感じた。
伊尹は厨人である。それが王の補佐の席にいた。奇蹟といってもよいことだった。庶民が政治を行ったのだ。
滅ぶ側に立つ者はそういう逸材を見えないだろう。伊尹は時の裂け目から現出したような人物である。
時を裂こうとしたのは湯王であり、裂かせまいとしてのが桀王である。それゆえに桀王には伊尹が見えるはずはないと望は思った。
受王の最盛期は十祀から十五祀までであろう。
その最盛期に差し掛かったころ、王朝転覆の陰謀があちこちで誕生していた。
望は馴の家を訪ねた。家には参がいた。
望はこの参こそが闇の帝王であることをわかっていた。参が仕えていた貴人の剣術と望の剣術は似ている。
二人は同じ人に仕えていたことがわかった。
望は兵法家にとって神のごとき存在となる。
神意によって軍を動かす時代にあって、用兵とか戦略といったものは発想されにくかった。
幸か不幸か、望だけはこの時代が持つ感情と信仰の外にいた。そうした望の合理に満ちた思想に最初に染められたのは向族であった。
望にとって最もわかりにくいのが周公であった。
周公に初めて会った人はその長身に驚いたはずである。だが、世間はそのことを知らない。なぜなのか。周公は自分のことを外に見せないように心掛けているのだ。周公は得体がしれない。
二載ほどまえには受王の左右には箕子と比干がいたが、いまは比干の代わりに費中がおり、費中によって政治が行われているといってもよかった。
そして、受王は盛大な祭典を催そうとしていた。後世「酒池肉林」と呼ばれるものである。
牧野の兵が沙丘に向かったということは周公を除く三公の陰謀が発覚したということだった。継を助けなければならない。
その継が生きていてくれた。
やはり三公は沙丘で誅殺された。驚くべき極刑だった。
望の目の眼底に涙がわいた。鬼公が殺された…。
そして、周公が捕らえられたとの情報が入ってきた。周公室の父子はそろって捕縛され、臣下は将兵と戦って死に、周公は獄へ投げ込まれ、嫡子の伯邑考の行方は分からなくなっていた。
周公を救う。
侠気とは違う。商王朝に対抗する力を持っているのが周だけで、ここで周公を失うと周も衰退してしまい、羌族が台頭するきっかけを失う。
望と小子旦が会った。周公の弟・南宮括も同席した。
望は小子旦に凶事を告げた。
その後、召へ向かうつもりになった。望の頭には常に召のことがあった。
時代の主役は沈黙し続けている。
周公である。かれこそ周王朝の基礎を築き、のちに文王と呼ばれる人物である。
いまは奴隷収容所内の獄につながれている。周公にとっての凶事は続く。嫡子が殺されたのだ。
その頃、周では二男の発を中心に対策が練られていた。かれこそはのちに武王と呼ばれる人物である。
発は望を知らない。発としてみれば、信用できないが賭するしかなかった。
馴が費中邸宅に出入りをしている。
その費中が妲己には自分でもはばからねばならないと漏らしていた。
望はそのことに興味を示した。権勢ならぶ者がいない費中をしてそう言わしめるほど妲己が大きくなっている。
望は会えないだろうかと思った。
恐ろしいものである。
妲己から光輝が放たれているような気がした。いまの艶麗さには直視できないほどの光がある。妲己は力を持ったのである。
望は妲己と話しているうちに、受王が祭祀の職を空洞化してしまおうとしていることがわかった。受王が王朝の体制を変革しようとしていることは明らかである。そのために妲己を利用している。
そして自分も妲己を利用しようとしていると望は思った。
望の戦いはようするに神と世間が相手である。その二つに勝てば、おそらく当面の敵は問題にはなるまい。目に見えぬ敵と戦うことがほんとうの戦いなのだろう。
蘇侯に望は知恵を授けた。
至上の策とは、それが策とは見えぬような策をいう。費中のような能吏を王宮の外から操るなど非凡さである。
西方の諸侯の訴えを費中がすすんで取り上げ、自分の過失をつぐなう。そういって蘇侯は費中に近づき、西方の斡旋者となり、周公に感謝される。
首謀者の望の影はどこにもない。
蘇侯は胸裡に寒気を覚えた。
小子旦は望の胸中に描いている未来図が見える男である。
周と商はいずれ戦う。その戦場の一つに何族の支配地がなるだろう。何族が周につけば、商は舟を使うことができない。逆もしかり。
小子旦はそれがわかるだけに、何侯には終始丁重に接した。
周公が獄から出された。
そしてやがて噂が流れ始めた。噂のもとと、伝播させているのは望である。虚空に受王像と費中像を描き、ことばにして世間へ流した。流言は飛語となる。
周公は商の東夷征伐の軍が十万と聞いて戦慄した。周軍は一万五千である。
双方が集めるだけ集めると、商が五十万、周が十万である。
周公には勝てる気がしなかった。いまは受王と戦う気はない。
周王は望に兵略の才があることはなんとなくわかる。だから軍事の意見を求めた。望は周王に戦いを見せた。模擬戦である。そして、一が三に勝つところを見せた。
周王は望に仕えてもらいたいと頼んだ。そして望は受けた。
勝った。
周軍の突風の様な攻撃で商の牙城が崩れた事実は受王の支配力に深刻な打撃を与えた。そして商王朝崩壊のきっかけとなる。
望が帰途につく中、ひとつの喬木に近づいた。十八年前、望たちがみた喬木であり、月下で黄金に輝いた喬木である。
喬木の下に剣が埋められているので、それをとりにいった。
望は召伯と会った。
召は周を完全には拒絶はしていなかった。そして羌族となら結んでいいといっている。
王朝内に反目がある。
その中で周王は崇を攻めた。それは崇侯たった一人を殺しただけの戦いだった。この戦い方を知った諸侯は周の軍門をおとずれ、帰属を乞うた。
周王は河水の両岸を制した。数年のうちに一大決戦が予想される状況になった。
受王は愕然とした。
だが、周王が崩御した。望はそれを聞き、目の前が暗くなった。受王の運の強さよ。太子発に諸侯がしたがうか。
望は太子の威光を知らしめる方法は一つしかないという。それは召伯を臣従させることである。
周召同盟が成った。
その出師は武王三年の冬に行われた。
長い商王朝を終わらせる出師であり、中国の古代史の中で一大異変を生じさせる出師でもあった。同時に神政下にある人々を宗教的呪縛から解放することにもなる出師だった。
周軍四十五万。商軍七十万である。
本書について
宮城谷昌光
太公望 上
文春文庫 約四九〇頁
目次
黄金の喬木
鬼方
いのちの渦紋
孤竹へ
伯夷の邑
老人と剣
朝歌
大河の光
春陰
落花流水
再会
闇の帝王
妲己
陰火
商の栄え
旅愁
疾走の時
長夜の宴
高貴な囚人
西方の風
機略
西伯
征伐
周と召
周召同盟
決戦
斉の邦
登場人物
望…のちの太公望呂尚
彪…羌族の少年たち
班…羌族の少年たち
呉…羌族の少年たち
詠…羌族の少年たち
継…羌族の童女
員…馬羌族、望の配下になる
受王…商王朝の王、紂王とも呼ばれる
箕子…箕邑の主、受王の叔父
鬼公…鬼方の首長
子良…鬼公の猶子
土公…土方の首長
斿…土公の臣
小子旦…周公の四男、のちの周公旦
旰…馬羌族の長の一人
仍…馬羌族の一人、旰の配下の十人長
呀利…馬羌族の一人、旰の側近
洞人…商の王子、望に剣と文字を教える
熹…孤竹の守護にあたる族長
鄭凡…交易に携わる大賈
逢尊…望に協力する東方の豪族
逢青…逢尊の娘、望の妻となる
飛廉…受王の臣、神足をもって仕える
参…商を恨む闇の組織の長
馴…参の養子
蘇侯…妲己の父
妲己…受王の寵姫となる