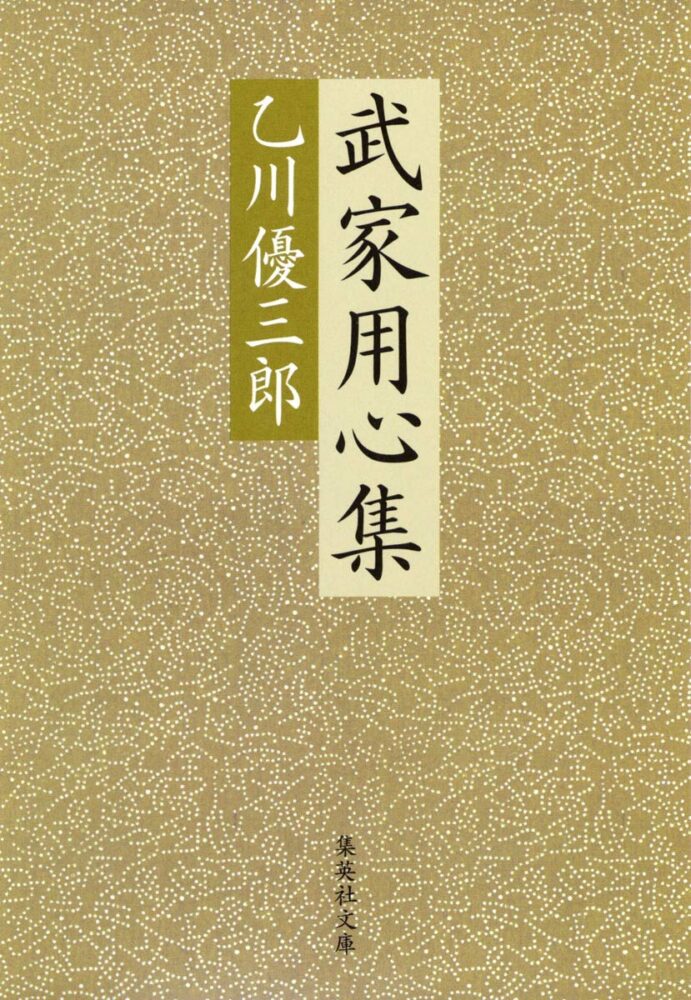第十回中山義秀文学賞受賞作品です。
淡々とした情景描写と、静謐なたたずまいを感じさせる文章と構成。秀逸の短編集だと思います。
「しずれの音」は老母の介護を巡る兄妹の問題を描いています。この家族構成が複雑なために、必然この問題も複雑になるのですが、最後の数ページは、感動的です。本当に涙が出そうになるシーンでした。
「九月の瓜」は藤沢周平の「三屋清左衛門残日録」を彷彿させます。
「うつしみ」がこの短編集を象徴するような作品だと思います。松江が祖母の津南を回想する形式ですが、この二人には血のつながりがなく、こうした血のつながりがない家族を描いた話です。
ですから、この中で語られるのは家族のことです。しかし、家族のことだけでなく、人間の強さ、弱さも描いています。読み終えた後に、深い余韻が残る逸品です。
「磯波」も同様に深い余韻の残る作品。
「梅雨のなごり」は伯父の大出小市の役回りがとても印象的です。
内容/あらすじ/ネタバレ
田蔵田半右衛門
倉田半右衛門が釣りを嗜むようになったのは八年前のことである事件に巻き込まれたのをきっかけに、人との接触を避ける方法がないかと考えていたころである。
その半右衛門を実兄の今村勇蔵が訪ねてきた。用件は家老の大須賀十郎を斬れというものであった。河川工事に関連して藩を欺いたためであるという。
半右衛門は念のために大須賀十郎の人となり、そして問題の河川工事のことを調べてみる。すると…
しずれの音
寿々が母・吉江の見舞いをし、兄の家を訪れることもしばしばであったが、ある時看病に疲れた兄・錬四郎の妻・房が実家に戻ってしまったので、しばらくの間母を預かってくれないかと頼まれる。
寿々は夫・周助に相談し、短期間であるならばということで引き受けるが、時期が過ぎても兄の家で引き取る様子がない。
九月の瓜
宇野太左衛門は勘定奉行であるが、隠居の日もみえてきた年齢にさしかかっている。
姪の祝言で桜井捨蔵の息子を見て、昔の記憶が甦った。それは、政変があったときのことであり、それまで二人はよく酒を酌み交わす中であった。この政変で太左衛門は捨蔵を蹴落として出世の階段を上り始めたのだった。
太左衛門は隠居を前にして、捨蔵に詫びをいいたくなってきた。
邯鄲
津島輔四郎は女中のあまとの二人暮らしである。あまは十四で奉公に来て六年ほどがたつ。あまは虫の音を真似ることが出来、いつしかこのあまの真似る虫の音が輔四郎の中で季節の移り変わりを告げるようになっていた。
そうして平安な日々が続く中で、忍びの頭・谷川次郎太夫を討ち取るように命が下された。
うつしみ
松江は夫の小安平次郎が束縛されてから落ち着かない日々を送っている。その松江が祖母・津南の墓参りに出かけた。思い出すのは祖母・津南に可愛がられ、様々なことを教え込まれた日々であった。
祖母・津南は波乱の人生を歩んできた人であり、それゆえに強さを持った人でもあった。
向椿山
江戸から岩佐庄次郎が医術の勉強を終え帰ってきたが、迎えには良順と千秋がいたのみで美沙生の姿はなかった。
帰ってきてから洩れ聞こえてくるのは美沙生に関する予想もしない話であった。庄次郎は嫉妬やら惨めな感情やらが入り交じり、治療を開始することが出来ないでいた。
磯波
奈津を妹の五月が突然訪れるのはいつものことであった。今日もそうである。五月は姉の奈津に縁談を持ち込んできたが、奈津はあまり興味がなかった。
五月の夫・直之進は父の門弟であり、奈津は直之進と夫婦になるものだと思っていた。だが、ある事があり、直之進は五月と夫婦になった。それから幾年も過ぎたが、奈津の心の中には直之進がいた。
梅雨のなごり
父・武兵衛の帰りが最近遅い。新しい藩主を迎えるにあたって、何やら仕事が立て込んでいるらしいが、同じ役の人が早く帰ってくるのを見るとどうも不安になるのである。母・つやが体のことを心配していると、利枝も自然と暗い気持ちになるのであった。
ある日、いつものように利枝の家に来て酒をちびちびと飲んでいる伯父の大出小市が、酔って帰ってきた兄の恭助を叱りとばした。この時に初めて父が如何に重要な仕事をしているのかを家族の者は知ったのである。
本書について
目次
田蔵田半右衛門
しずれの音
九月の瓜
邯鄲
うつしみ
向椿山
磯波
梅雨のなごり
登場人物
田蔵田半右衛門
倉田半右衛門
今村勇蔵
坪井孫兵衛
大須賀十郎
しずれの音
寿々
周助
吉江
錬四郎
房
九月の瓜
宇野太左衛門
片山晋太郎
桜井捨蔵
邯鄲
津島輔四郎
あま
一戸小藤太
谷川次郎太夫
うつしみ
松江
津南
向椿山
岩佐庄次郎
美沙生
良順
千秋
磯波
奈津
五月
直之進
梅雨のなごり
利枝
日比野武兵衛…父
つや
恭助
大出小市…伯父