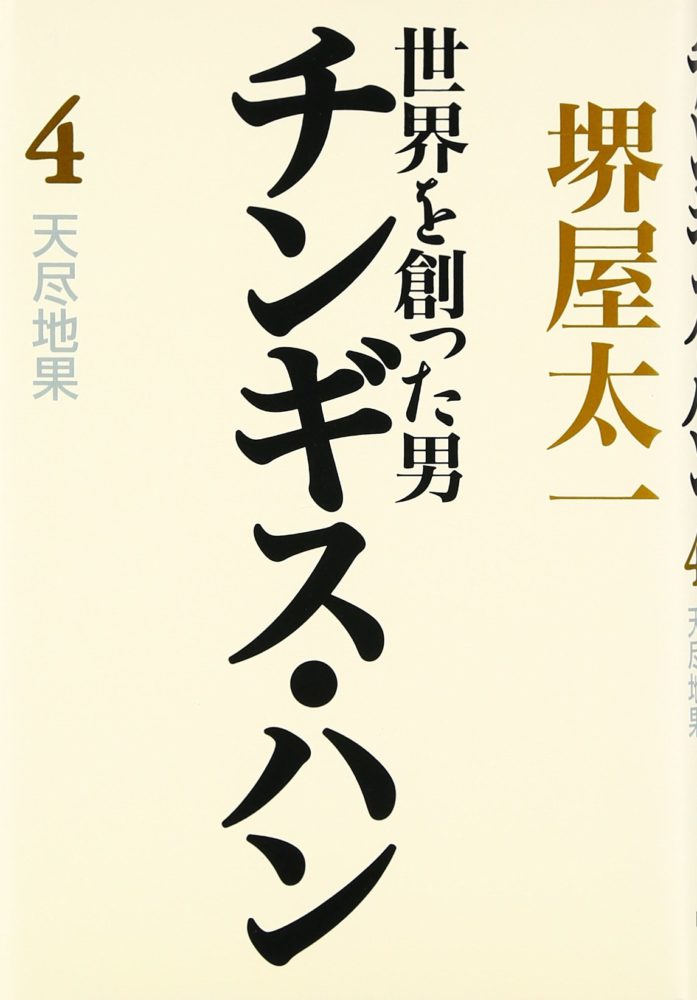覚書/感想/コメント
第四巻の題名は「天尽地果」。つまり、「天尽き地果てるまで」です。チンギス・ハンの晩年二十年間を描いています。史上最大の帝国を築いていく場面です。
大帝国を築く過程でチンギス・ハンが最初に攻撃をし、最後に征服したのが西夏です。西夏の歴史は詳しく分かっていません。通史がなく、漢字から作られた西夏文字も難解で、完全な解読はできていません。
チンギス・ハンと幕僚は情報の収集には熱心で、分析は冷静でした。このことは、これまでにも幾度となく堺屋太一氏は語っています。
これまで読むと、情報を有効に利用したからこそ、チンギス・ハンは広大な帝国を築き上げることができたのだと思ってしまいます。
チンギス・ハンの倫理は主観的ですが、知識は客観的でした。組織の上に立つものに必要な資質です。ですが、現実には逆になりやすいものです。世間の評判を気にして倫理は客観的になり、良い知らせばかりを聞かされ知識は主観的となります。
必要な情報をいかに滞りなく集め、自分の理念を遂行するために冷静に分析するかが大事ということです。
そして、その必要な情報をいかに滞りなく、かつ広範に集めてくるかが重要です。これには、多大な労力を人員がかかります。端的に言えば、金がかかるのです。
チンギス・ハンが広範で精巧な諜報機関を有していた情況証拠はしっかりとあるようです。
一つは、チンギス・ハン側の持つ情報がきわめて正確で濃密なことです。西夏の国王と皇太后の確執や、金軍の契丹族離反、ホラズム王国の皇帝と帝母の二重権力などを熟知していました。
逆に、チンギス・ハンと戦った相手は、金国、西夏、ホラズム、ロシアにしてもチンギス・ハンとモンゴル騎兵についてほとんど何も知りませんでした。
エジプトやヨーロッパでは、チンギス・ハンの子の代になっても、外見以外の知識はほとんどない状態でした。
第二には、攻撃を受けた側の民話や伝承にモンゴルの諜者らしき姿がいくつも描かれていることです。
ヨーロッパのモンゴル研究家の中には、伝承は広範囲であり、最西端は南フランスまで達しているといいます。
情報を得るとは、人を使うことであり、人を使うということは、金がかかるということです。現在でもその事はそのまま当てはまります。情報とは金です。情報の質が高ければ高いほど、値が張ります。
大モンゴル帝国を語る場合、征服戦争と同じくらい重要なのは通貨政策であるそうです。
それまでは、中華文化圏では銅(銭)が基本、天山山脈からホラズム領では銀河中心、エジプトやビザンチンでは金銀併用でした。漠北遊牧民の間では主として羊が役目を果たしていました。
それが、中華と中央アジアの統合により、全域で通用する国際基軸通貨として純度の高い銀を採用しました。銀本位制です。
ですが、大モンゴル帝国は、征服掠奪の発展期を過ぎると、財政と国際収支の双子の赤字を負うことになります。
それを補う役割を果たしたのが、不換紙幣でした。兌換を前提としないものです。このいかなる物質にも裏付けられていない不換紙幣が国際基軸通貨となったのは初めてであり、この次に現われるのは、一九七一年アメリカ政府が金ドル交換を停止した後の現在だけです。
一方の征服戦争えすが、モンゴル軍の破壊力と殺戮がクローズアップされる嫌いがあります。
実際に中央アジアのホラズム領におけるモンゴル軍の破壊と殺戮はどれくらいの規模だったのでしょうか。
ある年代記著者はヘラートで百六十万人、ニシャプールで百七十万以上が犠牲となったといいます。これよりあとのイスラムの歴史家は総数で千五百万人と推定しています。
ですが、これまでの発掘調査で、一都市で百万を超える人骨が発見されたことがありません。多い場合でも二、三万ほどだったそうです。
どうやら、イスラム圏では長い間傭兵たちのなれ合いの戦争が続いたので、モンゴル軍の大量殺戮が予想外の驚きを与え、それが誇張されて語られたのではないかというのです。
そもそも、この時代の中央アジアに、千五百万もの人間が住んでいたのかという素朴な疑問があります。
身内に対するチンギス・ハンですが、チンギス・ハンは諸弟に王傅をつけ、補佐役としてだけではなく監視の役も兼ねさせていた敵にも味方にも用心深かったといいます。建国の功臣はよく遇し、大功あったものを叛逆の嫌疑や過誤の罪で誅殺したことが一度もありませんでした。
そして、チンギス・ハンが死の直前に語ったという四人の息子の批評は次の通りでした。
「もし、狩猟に出て豊かな獲物にあり付きたいと思うのなら、ジョチの許へ行け。習慣と箴言を弁えたいのならチャガタイの許へ行け。寛大や賜り物の豊かさを願うのならオゴデイのところに近付け。名声や勇気や世界征服の夢を追うのならトルイに従え」
シリーズ全4作です。
- 世界を創った男 チンギス・ハン 第1巻 絶対現在
- 世界を創った男 チンギス・ハン 第2巻 変化の胎動
- 世界を創った男 チンギス・ハン 第3巻 勝つ仕組み
- 世界を創った男 チンギス・ハン 第4巻 天尽地果 本書
内容/あらすじ/ネタバレ
一二〇五年。東西三千キロ、南北一千キロの地域にチンギス・ハンに刃向かう勢力はなくなった。漠北遊牧民はチンギス・ハンの下に統一された。チンギス・ハンは可汗(大王)に推挙された。
正式な可汗就任前に、チンギス・ハンは域外遠征を成功させ、己の理念を衆に伝えようと考えた。遠征軍は西夏を攻めた。この戦いでモンゴル軍が城塞を攻撃したのは初めてだったが、猛攻により砦を陥した。西夏を滅ぼすには至らなかったが、莫大な戦果を得て凱旋軍が戻ってきた。
チンギス・ハンは自らの周辺に重要な三つの軍事機関を置いた。一つは「四匹の忠犬」の一人、クビライを長とする軍政本部、一つはコルコスンが創り上げた諜報機関、一つは強大な親衛隊である。
翌一二〇六年。部族集会(クリルタイ)が開催され、可汗の選出がされ、チンギス・ハンが可汗となった。これにあわせて、チンギス・ハンは功臣を称えた。第一位はムンリク、続いてボオルチュ、ムカリと続いた。
部族集会は七日間続き、国の規範について語った。これらは「大聖典」にまとめあげられる。国の仕組みにおいて、特色的なのは徹底した連座制である。一方で宗教には寛大だった。チンギス・ハンは「大聖典」を全ての人種、部族、家系のものに等しく適用した。
そして、大モンゴル帝国の行政機構の骨格となる断事官(司法)、書記官(行政)、宝庫官(財政)の三官制を調えた。
チンギス・ハンが可汗となった一二〇六年。西欧では第四次十字軍が失敗に終わった直後、日本では新古今和歌集ができた頃。
カスピ海から日本海に至るユーラシア大陸の中央から東よりには、三つの「帝国」がある。
できたばかりの「大モンゴル帝国」、西には「ホラズム帝国」、東の「金国」である。そして、この夏、金軍は南宋に大勝しており、ホラズム帝国も、皇帝ムハンマドがアフガニスタンのほぼ全域を征服していた。東西の帝国は戦勝に沸いていたのだ。
一方、チンギス・ハンは難問が生じており、その解決にボロクルを派遣するが命を落とすことになる。チンギス・ハンは悲しみ、己の迂闊さを恥じ、この様な叛乱を二度と起こさせないために、チョルマカンのタマチ軍団を派遣して残らず殺し尽くさせた。
逆上による残虐ではない。信仰や人種の違いによる虐殺でもない。長期的な平和の保持のための計画的な大量報復戦略である。これが統治手法として確立される。
金国の皇帝が替わった。一二〇八年のことだった。だが、チンギス・ハンは慎重で金国攻撃ではなく、三度目の西夏攻撃を命じた。この戦いではチンカイの率いる工兵隊をともなった。この戦いで西夏はチンギス・ハンと和を結ぶ。
チンギス・ハンほど味方の命を惜しんだ軍司令官はいない。味方の安全のためなら、捕虜や住民を殺し、都市を壊すのを躊躇しなかった。
この戦いは半分訓練のようなものであり、攻城戦の研究、武器の研究などがなされた。
そして、一二一〇年、金国遠征に向けて本格的に動き出す。
チンギス・ハンが金国侵略の大号令を発したのは一二一一年の春だった。総数五万五千騎。
金国は大軍を擁していたが、南宋、西夏、契丹人の叛乱に兵力が分散され、チンギス・ハン軍のそしをできなかった。当時の金国は士気も高く、崩れかかった弱敵と戦ったのではなかった。
結局、チンギス・ハンは一二一二年のはじめに一時撤退を余儀なくされる。この戦いでの被害も大きく、チンギス・ハンはこの一年の戦いは失敗であったと断じ、原因を考える。
翌一二一三年にチンギス・ハンは再び金国攻略の軍を興す。今回の戦いにおいてはチンギス・ハンは戦争目的の徹底と戦術概念の周知を重視した。
今回の戦いでは、モンゴル軍は九十の都城を陥落させた。
そして一二一四年、チンギス・ハンは全軍撤退をさせる。人口膨大な農耕文化を統治する人材と知識が足りなかったためでもある。
そして、再度金国に攻める。一二一五年。中都を陥落させた。このとき耶律楚材を得る。
チンギス・ハンは西夏でも金国でも、ホラズム帝国でも一度の軍事的勝利だけで占領統治をしようとはしなかった。西夏は四度、チンギス・ハンが一度、ムカリが二度目、子の代になって三度目の勝利後に統治している。
この勝利後、チンギス・ハンのもとにホラズム帝国からの使者がやってきた。このとき、二国間の間いたメルキトの残党や亡命王子グチュルクの存在を知り、これを討伐する。そして、チンギス・ハンの勢力とホラズム帝国が直接ふれあうこととなる。
ホラズム帝国との摩擦が生じ始めた頃、チンギス・ハンは後継者を選定することにした。後継者は三男のオゴデイに決まった。後継者はオゴデイだが、チンギス・ハンの身辺にはトルイが付き従い、強大な政府機構と親衛隊を継承したのはトルイだった。帝位の継承者と実力の相続人が異なることとなる。
チンギス・ハンは一二一八年末に西征に旅立つ。総兵力十万以上。もはや軽騎兵集団ではなく、動く移動都市と化していた。
対するのはホラズム帝国。一二一九年頃は帝国の最盛期だった。チンギス・ハンが戦い、倒した相手は金国にしろ、ホラズム帝国にしろ、弱い相手ではなかった。
要衝オトラルが陥落したのは一二二〇年のことだった。そのころ、チンギス・ハン自身は大都市ブハラに迫っていた。
ここで、チンギス・ハンは「汝らは罪を犯した。朕は天の意向によりここに来た。汝らが罪を犯さなかったら、天は朕を汝らの頭上に差し向けなかったであろう。朕は天が罪深き汝らに降した災難である」と演説した。そして、ブハラ陥落にホラズム帝国の首都サマルカンドは震駭した。
皇帝ムハンマドは、チンギス・ハンの侵攻からわずか二年で乞食同然の身となって世を去った。
チンギス・ハンが長春真人に宛てた手紙というものが残っている。そこには自己分析が示されている。
「朕には、特に際だった資質が備わっていない。朕が勝てたのは、朕の武勇がすぐれていたからではなく、敵の能力が足りなかったからだ。
天は、わが周辺の富み栄える国々を、傲慢と奢侈の故に罰した。朕は今も、馬飼いや牛飼いと同じものを着、同じものを食べている。わが君臣は労苦を共にし、富と栄えを共有している。朕は贅沢を憎み、節制を旨としている」
「朕は臣下の者をわが子のように扱おうと努めている。才あるものは氏族身分に関わりなく兄弟のように遇した。朕と臣下とは常に原則において一致し、愛情によって結ばれていた」
史書の記述も、発掘調査の結果も、この言葉が偽りでなかったことを示している。
本書について
堺屋太一
世界を創った男 チンギス・ハン4 天尽地果
日本経済新聞出版社 約二九〇頁
モンゴル帝国 13世紀
目次
『国』を肇る
戴冠
三人の皇帝
「天」と競う
機、熟す
天下騒然
勝つも治めず
「道」を拓く
負ける理由
「朕は災難である」
「世界」を創る
久遠の蒼穹
「志なお止まず」
第四巻の注釈
登場人物
(家族)
チンギス・ハン…大モンゴル帝国を築く
ボルテ…チンギスの妻
ホエルン…チンギスの母
ジョチ…長男、キプチャク汗国の始祖
チャガタイ…二男、チャガタイ汗国の始祖
オゴデイ…三男、チンギスの後継者
トルイ…四男
カサル…チンギスの次弟
(部下)
ボオルチュ…右翼万戸隊長、「四頭の駿馬」(四駿)
ムカリ…左翼万戸隊長、「四駿」
ボロクル…右翼万戸隊副長、「四駿」
スボタイ…西方大遠征の司令官、「四狗」
ジェベ…西方大遠征の司令官、「四狗」
チョルマカン…隷属民出身。タマチ軍団を率いる
コルコスン…ウイグル人の旅芸人。諜報機関の創始者。
ヤラワチ…ムスリムの財務長官、通貨の普及者
シギ・クトク…タタル族の遺児。チンギスの義弟。検事総長兼最高裁長官
チンカイ…ケレイト人。建設運輸長官
耶律阿海…契丹人の部隊長
耶律留哥…チンギスの援護で「遼王」となる
耶律楚材…契丹人文官
ハッサン…イスラム教徒の隊商親方
テプ・テンゲリ…祈祷師。ムンリクの二男
コルチ…バリン族の祈祷師
(他の人々)
襄宗(李安全)…西夏王
衛紹王…金朝七代目皇帝
ムハンマド…ホラズム帝国の皇帝
ジェラール・ウッディーン…ムハンマドの長男