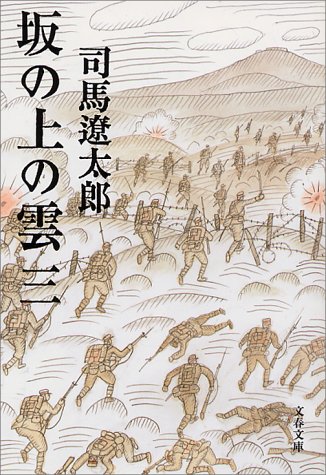文庫第三巻。
この巻で、正岡子規が死にます。そして、話は日露戦争へと進んでいきます。
この巻から先に関しては、どう読むかによってだいぶ印象が異なって来るでしょう。
司馬遼太郎氏は『明治の悲惨さは、ここにある。』と語っています。
氏の語るかたるそれは、次の通りです。
『日本の国家予算である。
狂気とでも言うべき財政感覚であった。
日清戦争は明治二十八年におわったが、その戦時下の年の総歳出は、九千百六十余万円であった。
翌二十九年は、平和の中にある。当然民力をやすめねばならないのに、この二十九年度の総歳出は、二億円あまりである。倍以上であった。このうち軍事費の占めるわりあいは、戦時下の明治二十八年が三二パーセントであるのに比し、翌年は四八パーセントへ飛躍した。』
『-(略)-われわれが明治という世の中をふりかえるとき、宿命的な暗さがつきまとう。貧困、つまり国民所得のおどろくべき低さがそれに原因している。』
明治時代には、結果として日清戦争と日露戦争が起きるわけですが、司馬遼太郎氏は、『日露戦争というのは、世界史的な帝国主義時代の一現象であることはまちがいない。が、その現象のなかで、日本側の立場は、追いつめられた者が、生きる力のぎりぎりのものをふりしぼろうとした防衛戦であったこともまぎれもない。』と語っています。
この一文をどう捉えるかは人それぞれであろうかと思います。
この当時の政府要職の心情を表現している箇所はいくつも出ていますが、現場の軍人の心情を書いた場面というのも書かれています。
それは、秋山真之の同期で、生涯の友人だった森山慶三郎が、旗艦三笠の長官公室にあつまり、出撃の命令が伝えられた時の模様を語るところで、下記のとおりですが、悲壮感が漂い、勇ましさはどこにもありません。
『「私はただうつむいてだまっていた。涙がこぼれて仕方なかった。満座のひとはひとりとして顔をあげる者がいない。たれひとり声もあげず、まるで深山のようであった。」
森山の述懐では、このとき脳裏を去来したのは、ロシアに負けるかもしれないということであった。-(略)-ポーランドを過ぎてその亡国の状を見た。戦勝者のロシア人が、どの町でもその町の主人のような態度でポーランド人を追いつかっているのをみたが、-(略)-日本もあのようになるのではないかとおもうと、感情の整理がつかなくなり、涙がとめどもなくなった。』
また「あとがき」にこう書かれています。
『日本政府の要人のほとんどが戦争回避論者であった。なかでも元勲の伊藤博文が非戦のための先鋭的存在だったことは、伊藤という人物がいかに愛国的ファナシズムにまどわされず、いかに政治家として現実主義的思考をくるわさずに生きえたかという点であらためて評価を重くしてやってもいい。』
一方で、同じく「あとがき」にマスコミや学者などを非難気味に書いています。
『日露戦争前、政府はもっぱら避戦的態度であり、自然、政府系の新聞とされる国民新聞や東京日日新聞は自重論であり、-(略)-
民衆はつねに景気のいいほうでさわぐ。むろん開戦論であった。この開戦への民衆論を形成したのは朝日新聞などであった。学者もこれに参加した。帝大七博士といわれるひとびとがそれで、七人が一小党をなして政府にはたらきかけた。
「きょうは馬鹿七人がきた」
と、自宅の応接室から出てきて、ぼんやり顔でつぶやいたのは、この時期の参謀総長大山巌であった。』
小説(文庫全8巻)
NHKのスペシャル大河「坂の上の雲」(2009年~2011年)
内容/あらすじ/ネタバレ
秋山真之が帰国したのは明治三十三年夏である。翌年には海軍少佐にすすんだ。
このころ、いよいよ海軍戦術の研究に熱中していた。この当時、日本海軍にあって、戦術家と自他ともに許される人物は、真之の先輩では島村速雄と山屋他人の二人しかいなかった。
海軍大学校に戦術講座が設けられたのは、明治三十五年のことだった。戦術というものの系統だった研究に初めて日本海軍は乗り出し、真之が初代教官に選ばれた。
真之の戦術講義は、不朽といわれるほどの名講義だったようだ。原典はつかわず、彼自身が組織して体系化した海軍軍学のみならず、その組織に至までの秘訣をくりかえしおしえた。海軍の先輩までもが聴講生で入ってきた。
この学生が、日露戦争とともに各戦隊の参謀として配属され、真之のもとに秋山戦法を個々に実施した。このため、作戦面ではほとんど一糸乱れぬ結果を得る。
東京に移って、真之は一度正岡子規を見舞いに行った。一別以来、別人のように衰えていた。結局、この時の見舞いが真之と子規との最後の対面となる。
子規が死んだのは明治三十五年九月十九日の午前一時であった。真之が子規の死を知ったのは、横須賀線に乗っている時であった。
日本の政治家のほとんどは、ロシアと戦って勝てるとは夢にも思わなかった。伊藤博文は、恐露家というあだなをもらっていた。そのロシアが極東を侵略して圧迫してきている。
日本は四方を海に囲まれている。海軍を強化しなければならず、それをやってのけたのは山本権兵衛(ごんのひょうえ)であった。権兵衛(ごんべえ)と世間ではいう。
当時の国家予算に占める軍事費の割合は日清戦争の戦時下であった明治二十八年で三十二パーセント、戦争が終結している翌年の明治二十九年は四十八パーセントだった。
明治二十九年にスタートする建艦十カ年計画が実施された。国家予算の総歳出がいよいよふくらんだ。明治三十年には軍事費が五十五パーセントであった。
日清戦争のころの日本海軍は、海軍とは名のみの軍艦が多く、戦艦も持っていない。一等装甲巡洋艦もない。だが、戦後十年の日露戦争直前には、世界の五大海軍国の末端に連なるようになった。
山本権兵衛は大佐か少将の身で大改革をやりえた。西郷従道が上司であった。
権兵衛が日清戦争の前にやった最大の仕事は、海軍の老巧、無能幹部の大量首切りだった。
これによって「薩の海軍」は事実上ほうむられた。この時に海軍大佐東郷平八郎もリストにのぼっていたが、様子を見ることとなり、首がつながっている。
権兵衛は二度海軍を設計した。それは日清戦争と日露戦争であり、それぞれ準備に十年かけている。
ロシアの南下による重圧をなんとか外交手段で回避できないかと考えた。伊藤博文は、いっそロシアと攻守同盟を結んでしまったらどうかと考えていた。
そのころ、英国がひそかに極東の事態について関心を高めつつあった。あるドイツ外交官が日英独同盟を画策し、これからやがて日英同盟がうまれることになる。
この当時の外務省は英国と同盟したかった。だが、国力といい、他の要素を鑑みて、対等の同盟を英国に持ちかけることは不可能であった。
ひとり、駐英公使の林董がよく働いた。英国の態度は、日本にとってほとんど奇蹟的であった。
この頃に内閣がかわった。桂太郎が総理大臣となる。外相には小村寿太郎らがつき、日露戦争の遂行内閣となる。
ちょうど伊藤博文が外遊することになっていた。この伊藤の外遊行動が日英同盟の締結を早めることになる。伊藤が働きかけたためではない。伊藤がロシアを訪問した事によるものであった。
この少し前、海軍少佐広瀬武夫がロシア駐在武官の任務をとかれて日本に帰ってきていた。広瀬のロシア駐在は足かけ六年に及んだ。広瀬は秋山真之に見聞してきたロシア海軍の実体を話した。
明治三十六年。秋山好古は習志野にある騎兵第一旅団長に補されていた。四十五歳の少将だ。
好古が騎兵本来の現場に戻ったのは、日本陸軍が取りつつある臨戦態勢の現われの一つである。日本騎兵をひきいるのは秋山好古以外にいないというのが定評であった。
ロシアから妙な招待状が届いた。シベリアでロシア陸軍の大演習を行うので、参観武官を差遣されたいというものだった。秋山好古と大庭二郎歩兵少佐を出すことにした。
ロシアは世界第一の陸軍の威容を見せて日本人の戦意をくじくつもりだ。だが空振りに終わる。
演習が終わり、好古は騎兵の用語でいうところの「威力偵察」をしてやろうとおもった。満州との境界のシベリアは、最大の機密地帯である。
日本の参謀本部も知りたがっているが、いくら間諜を入れても核心をついた報告がない。
好古の偵察は成功した。結局満州の核心部まで及び、さらに南下して旅順へゆき、軍事施設を見学した。開戦前に旅順の軍事施設を見たものは、間諜ですらおらず、好古だけだった。
秋山好古が東京に戻った明治三十六年の日露間の外交情勢はどうにもならないほど悪化していた。
弟の真之がにわかに常備艦隊の参謀に補された。戦時にはそのまま連合艦隊の参謀となる。この前に真之は結婚していた。
真之が参謀になるにはいきさつがある。海軍省人事局がその戦いの人事の事務局となっている。
まっさきに、艦隊作戦のすべてを、三十六歳の少佐秋山真之にやらせることが決定した。同時に司令長官を決定した。中将東郷平八郎である。
この明治三十六年。渋沢栄一の事務所に陸軍中将児玉源太郎が訪ねた。日露戦争の陸軍作戦を、この不世出の作戦家といわれた男が担当する。
児玉が渋沢を訪ねたのは、軍費に関して、非戦論者である渋沢を説得するためのものであった。一端は物別れとなったものの、近藤廉平の報告によって、渋沢の気持ちが変わる。
この短い期間に児玉はそれまでの職より低い参謀本部次長の席にみずから志願してついた。
渋沢は勝算を聞く。児玉は勝つところまではゆかない。優勢なところまでもってゆき、あとは外交だ。時が移れば移るほどロシアに有利になる。
今なら何とかなる。日本は万死に一生を期して戦うほかに、残された道はないという。
ロシアのニコライ二世は「朕が戦いを欲しない以上、日露間に戦いはありえない」といった。その間にも、極東に兵を送り込み、銃剣外交の威力を高めた。ロシア側としては日本が開戦をすることはないと踏んでいたのだ。
日本政府が対露開戦を決意したのは、明治三十七年二月四日の最後の御前会議においてであった。
このときの陸海軍には、日本が勝という確実な見込みを持ったものは、誰一人いなかった。もはや成功不成功を論じている余裕はなかった。
陸軍の児玉源太郎も五分五分がやっとだという。海軍の山本権兵衛も児玉と同じようなことをいった。
日本はロシアに国交断絶を通告したのは、明治三十七年二月六日であった。
日本の戦略の主眼は、短期間にできるだけはなやかな成果をあげ、あとは外交によって和平にもちこむというものであり、これを外してこの戦争は全くなりたたない。政府要人の全員が分かっていることであった。
山本権兵衛統裁による日本海軍の戦略は、ロシアの二つの海軍力が合体しないように、まず極東艦隊を沈め、ついで本国艦隊をむかえて沈めるというものであった。日本の艦隊は、ロシアの二つの艦隊の一つとほぼ同兵力であった。
旗艦三笠にロシアとの断交の通知が告げられた。東郷平八郎以下、連合艦隊は旅順口及び仁川港にあるロシア艦隊の撃滅のため出発した。
連合艦隊参謀長は海軍大佐島村速雄であった。山本権兵衛が東郷平八郎のためにつけたのであり、その島村は作戦のすべてを秋山真之に一任し、終始その通りとした。
海軍に課せられた緒戦での任務は、旅順艦隊を撃って制海権を確立することと、仁川に陸軍部隊を揚陸することだった。
連合艦隊にとって主力は旅順を襲うことであり、仁川襲撃は別働隊の仕事だった。
主力による旅順での奇襲作戦の結果は思わしくなく、一隻も沈めることができなかった。
また、旅順口外の海戦と呼ばれた海戦でも日本側は必ずしも成功していない。
それに、旅順のロシア海軍は、日本側とほぼおなじ兵力を持っているにもかかわらず、要塞艦隊主義を取り、湾内深くにひきこもって要塞に守られるかたちとなった。
東郷は旅順要塞と戦いたくなかった。何とかロシア艦隊を引きずり出して沈めなければならない。それはバルチック艦隊が到着するまでにやらねばならないことである。
旅順を閉塞する作戦がとられた。真之が米西戦争の時に見た作戦を行うというのだ。真之は消極的だったが、数度にわたってこの作戦が決行される。
陸軍の戦略は、第一軍を朝鮮に上陸させ、満韓国境に布陣しているロシア軍を撃破し、第二軍をもって遼東半島に上陸させ満州中央部に北進して第一軍とともに遼陽の平原でロシア主力と大決戦をおこなって破るというものだった。
児玉源太郎はこれ以外にないというところまで作戦を練った。
第一軍は大将の黒木為楨、第二軍は奥保鞏で、秋山好古の騎兵は第二軍に属した。
海軍はマカロフ中将ともども旗艦を沈めることに成功する。だが、このあと、海軍は敵の砲火をうけることなしに、八隻を失うことになる。今後、この戦争をどう戦うのか。現場での艦長達は茫然とする思いであった。
本書について
目次
十七夜
権兵衛のこと
外交
風雲
開戦へ
砲火
旅順口
陸軍
マカロフ
関連地図
登場人物
秋山信三郎好古…兄
秋山淳五郎真之…弟
正岡升子規
お律…子規の妹
お八重…子規の母
高浜清(虚子)…池内信夫の四男
河東秉五郎(碧梧桐)
寒川鼠骨
陸羯南…正岡子規の生涯の恩人、「日本」社長
稲生季子…秋山真之の妻
小笠原長生…海軍少佐
八代六郎…海軍大佐
伊藤博文
西郷従道…海軍大臣
山本権兵衛…大佐、少将
ヘルマン・フォン・エッカルトシュタイン…ドイツの駐英代理公使
ジョセフ・チェンバレン…イギリスの植民大臣
青木周蔵…外務大臣
林董…日本の駐英公使
桂太郎…内閣総理大臣
小村寿太郎…外務大臣
広瀬武夫…海軍少佐
大庭二郎…歩兵少佐、のち陸軍大将
ミルスキー…ロシアの大尉
ウォルノフ…ロシアの大佐
リネウィッチ…ロシアの大将
東郷平八郎…中将、連合艦隊司令長官
島村速雄…連合艦隊参謀長、のちに元帥
森山慶三郎…海軍少佐、のち中将
日高壮之丞…前常備艦隊司令長官
田中保太郎
千秋恭二郎
山口鋭
渋沢栄一
近藤廉平
大山巌…陸軍大臣
児玉源太郎…陸軍中将
黒木為楨…陸軍大将、第一軍
奥保鞏…第二軍
金子堅太郎
ニコライ二世…ロシア皇帝
ウィッテ…ロシアの重臣
ベゾブラゾフ…ロシアの重臣
アレクセーエフ…関東州総督
マカロフ…ロシアの海軍中将