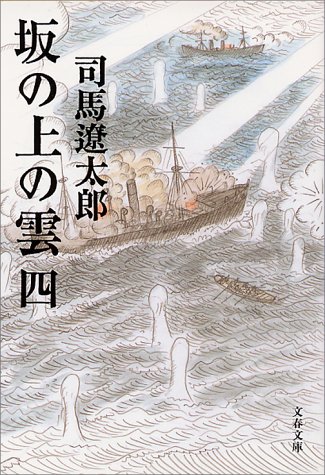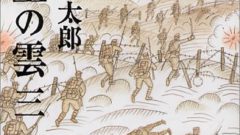文庫第四巻。
この巻ではひたすら旅順攻略に苦しむ日本軍の姿が描かれ、司馬遼太郎氏はその苦戦の原因を一人の人物に絞って、何度も何度も口のかぎり罵倒しています。
それは、第三軍乃木希典の参謀長となった少将伊地知幸介です。
参謀長となった伊地知幸介は、乃木希典が長州出身であるため、バランスをとるためにえらばれています。能力ではありません。
この時期、海軍は山本権兵衛によって薩摩閥から脱却していましたが、陸軍は山県有朋が大鉈を振ることをしなかったため、旧泰然とした人事となってしまったのです。
この伊地知幸介については、司馬遼太郎は以下のように罵倒し始め、本巻の最後までその姿勢は変わらりません。
『多年ドイツの参謀本部に留学していた人物で、しかも砲兵科出身であった。砲兵科出身の参謀長でなければ要塞攻撃には適任ではないであろう。ところがこの伊地知が、結局はおそるべき無能と頑固の人物であったことが乃木を不幸にした。乃木を不幸にするよりも、この第三軍そのものに必要以上の大流血を強いることになり、旅順要塞そのものが、日本人の血を吸い上げる吸血ポンプのようなものになった。』
『有能無能は人間の全人的な価値評価の基準にならないにせよ、高級軍人のばあいは有能であることが絶対の条件であるべきであった。かれらはその作戦能力において国家と民族の安危を背負っており、現実の戦闘においては無能であるがためにその麾下の兵士たちをすさまじい惨禍へ追いこむことになるのである。』
一方、乃木希典へは下記のとおり、ある意味同情的ですらあります。
『乃木希典の最大の不幸は、かれの作戦担当者として参謀長伊地知幸介がえらばれたことであった。乃木に選択権があったわけではない。陸軍の首脳がそれをえらんだ。』
旅順攻撃に関しては、「災害」という言い方すらしています。
『旅順における要塞との死闘は、-(略)-もはや戦争というものではなかった。災害といっていいであろう。』
『旅順の日本軍は-(略)-ののしられている参謀長を作戦頭脳として悪戦苦闘のかぎりをつくしていた。一人の人間の頭脳と性格が、これほど長期にわたって災害をもたらしつづけるという例は、史上に類がない。』
その「災害」は必ず二十六日に起きます。なぜなら、総攻撃は必ず二十六日に行われたからです。ロシア側はこの総攻撃を事前に予測して準備をしていました。
二十六日総攻撃の理由を伊地知参謀長はこういいます。
理由は三つあります。
一つは火薬の準備であり、導火索は一月保つので、前回から一ヶ月目になるということ。ですが、これは科学性に乏しい。
二つ目は、南山を攻撃して突破した日が、二十六日で縁起がいい。
三つ目は、二十六という数字は割り切れる。つまり要塞を割ることができる。
司馬遼太郎氏は『この程度の頭脳が、旅順の近代要塞を攻めているのである。兵も死ぬであろう。』といっています。
ここまで伊地知幸介を罵倒している司馬遼太郎氏の気持ちというのは、本巻の最後に、児玉源太郎の言葉として語られる次の言葉に象徴されるのかもしれません。
『司令部の無策が、無意味に兵を殺している。貴公はどういうつもりか知らんが、貴公が殺しているのは日本人だぞ』
乃木希典を扱った作品に「殉死」があります。
小説(文庫全8巻)
NHKのスペシャル大河「坂の上の雲」(2009年~2011年)
内容/あらすじ/ネタバレ
陸軍は満州に上陸したものの、その後の戦闘は必ずしも上手くいっていない。
現地の状況がよく分からないため、児玉源太郎は高等司令部を現地に作ることを決めた。それは参謀総長である大山巌と、次長である自分が東京から離れて現地に移動することである。
遼陽の大会戦がせまっている。
旅順に対する陸軍の感覚は鈍すぎると秋山真之はつねに感じていた。今海軍は旅順をふさいでいるが、隊員にとっては休息もなく、長引けば、軍艦も艦底にカキがつき、機関に老廃物が蓄積して、出力も速力も落ちていく。
このままではロシアの本国艦隊が着た時に、本来のスピードが出ず、それによって負けるかもしれない。
要塞化された軍港内にいる艦隊を外洋に追い出して沈めるしかない。そのためには陸から追い出すしかない。
陸軍参謀本部は旅順を攻めるのをためらったが、第三軍を創設し、乃木希典を軍司令官とした。参謀長には伊地知幸介、砲兵部長に豊島陽蔵らが配された。
海軍が献策していたのは、二〇三高地を攻めてもらいたいということであった。東郷艦隊が洋上から見ると、この山が盲点であることがよくわかるのだ。
これを最初に見つけたのは秋山真之だった。
この山が旅順港を見下ろすのにちょうどいい位置を持っていることが重要だった。この山の上から大砲を撃てば、簡単にロシア艦隊を撃てる。
艦隊を追い出すための作戦である以上、これは必要かつ充分なはずであった。
だが、伊地知幸介は一笑に付し、しかも、陸軍には陸軍の方針があるとして、大要塞の玄関口から攻める、真正直な戦法をとった。
二〇三高地については、児玉源太郎が総司令部の仕事を一時捨てて、旅順に自らでむき、作戦の主導権を握ることで、海軍案を採用したことで奪取することができた。
これにより、旅順攻撃は急転換した。はじめ旅順は一日で陥ちるはずであった。だが、百九十一日を要し、日本側の死傷六万人という世界戦史にも未曾有の流血の記録を作った。
のちに「黄海海戦」と呼ばれる、日本にとってもロシアにとっても惨憺たる海戦が行われた。旅順艦隊司令長官のウィトゲフトの大決断からおこった。
極東総督アレクセーエフから皇帝の意思として伝えられたのは、すみやかに出港してウラジオストックへ行けという命令だった。それに従ったのだ。
出港してきた艦隊を前に、東郷艦隊は迎え撃つことになるが、秋山真之はどう考えてもわが方に勝ち目があるはずがないと思っていた。艦隊兵力の差が歴然としていた。しかも東郷に課せられた使命は「殲滅」であった。
その上、長い封鎖作戦に疲れていたのか、東郷とその頭脳達は、単純な敵の意図を誤算した。
ともかくもウラジオストックへというのがウィトゲフトの方針である以上、日本艦隊を見ても逃げ切ることしか考えていない。だが、東郷艦隊は出撃と思っているので、敵を誘い込む運動をしている。
おかしいと感じてから、今度はウィトゲフトを逃がさないために東郷艦隊は全力で追いかけ始める。だが、初期において無駄な運動をしたため距離が空いてしまっていた。
東郷の追跡は悲愴だった。勝者の追跡ではなく、追わなければ敗者に転落する追跡だった。そして滑稽なのは、大兵力が逃げ、小兵力が追っていることであった。
この戦いは、東郷とその幕僚の苦い経験となり、日本海海戦の時の教訓となっている。
東郷艦隊がなんとかロシア艦隊に追いつけたのは、ロシア側に故障した戦艦がでたことによる。
戦闘になった。日本の砲弾は、敵艦を沈めることよりも戦闘力を奪うことに主眼がおかれている。その砲弾の一つがウィトゲフト以下の幕僚を吹き飛ばした。
運命的なのは、砲弾が操舵員をたおしたことだった。舵にのしかかり、舵が左へと回ったまま操舵員は絶息した。戦艦が左へ回り始め、後続の戦艦は戦術的方向変回をしようとしていると判断することになる。
だが、実情はことなる。この混乱から始まり、ロシア側は各艦がどこへ行っていいのか分からなくなる。
それでも、日本側は各艦を大破させてはいるが、一艦も沈めていない。作戦目的を達せられなかったという基準において、黄海海戦は失敗に終わった。
幸いだったのは、ロシア軍艦は黄海では一艦も沈まないのに、みずから敗北の姿勢をとり、武装解除したことである。一部は旅順へふたたび逃げ込んだ。
クロパトキンは遼陽に大軍を集結して日本軍を一気に殲滅するつもりでいる。
この会戦は野外決戦でありながら、要塞の要素をふんだんに入れ、遼陽城を要塞化し、前面の山野も加工した。クロパトキンの兵力は二十三万、日本軍は十四万であった。
日本軍はすでに砲弾が足りなくなっている。戦いの準備期間中から、近代戦における物量の消耗を想像し得なかったのだ。これは日本陸軍の体質的欠陥というべきものだった。この計画を建てたのは陸軍省の砲兵課長であり、この立案の失敗が、国家の運命を左右するところまできていた。
補給の欠乏は、戦闘の勇敢さをもってカバーせよ、というのが大本営の意思であった。
秋山好古の騎兵旅団は主力の左翼に位置していた。本来防御に適さない騎兵を防御に回しているため、防御のための編成を要求した。これによって、好古の旅団は、ロシアのコサック騎兵集団を率いるミシチェンコ旅団以上の戦力を持つことになる。
この秋山支隊が奥軍主力よりも遙か北方に進出して、敵の内側にはりこんでその右翼に痛烈な攻撃を加えた。ロシア側の記録によると、この騎兵砲中隊の威力はすさまじかった。
遼陽会戦を勝利に導いた最大の功績は第一軍の黒木軍だろう。黒木軍は主力ではなく、一種の遊軍のような役割だったが、ロシアのクロパトキンとその幕僚を強く意識させていた。
やがて、ロシアは負けていないのに、遼陽そのものを放棄することになる。クロパトキンには奉天があるという思いもあったようだ。遼陽での攻防戦で、日本軍の死傷は二万で、ロシア軍もほぼ同数だった。
この戦いでの日本軍は、各国から来た従軍記者のあしらいが下手で、そのため微妙な結果となった遼陽の会戦のニュースは日本軍非勝利として世界中をかけまわる。日本公債の応募は激減し、戦時財政に手痛い衝撃をあたえることになる。大本営は多少慌て、日本帝国の元老は飛び上がるほどにおどろいた。日本には金がないからだ。
旅順は日本の陸海軍にとって最大の痛点でありつづけた。東郷艦隊は陸軍がこの要塞をおとさないかぎり、釘付けとなる。仮に旅順が落ちても、艦隊の修理に最低二月はかかる。各艦を修理して機能回復せねば、バルチック艦隊に勝てる見込みはない。
東京の大本営も焦りに焦った。乃木では無理だったという評価がすでに出ており、参謀長の伊地知幸介の無能についても、乃木以上にその評価が決定的になりつつあった。更迭説も出ていたが、戦いの中での更迭は、士気という点で不利だった。
乃木軍が第一回総攻撃を始めた。これによって強いられた日本兵の損害は、わずか六日間の猛攻で死傷一万五千八百であり、敵に与えた損害は軽微、小塁ひとつぬけなかった。第二回目の総攻撃では死傷四千九百人で、要塞はびくともしない。
東郷艦隊の幕僚室では、なぜ乃木軍は二〇三高地に攻撃の主力を向けてくれないのかと思っていた。東京の大本営にとっても、乃木軍の作戦のまずさとそれを頑として変えようとしないのは、すでにガンのようになっていた。大本営でも二〇三高地を攻めるように頼んだが、命令系統のこともあり、示唆程度に終わる。
東京では少将有坂成章が長岡外史に、二十八サンチ榴弾砲を送ってはどうかという。これが日本敗亡の危機から救い出すことになる。
遼陽での勝利は地をえただけにすぎない。それに、日本は国力の貧弱さのために遼陽からの跳躍力をうしなった。まず砲弾が足りず、児玉源太郎は砲弾を溜めることに「作戦」の重点を絞らざるを得なかった。
児玉源太郎が留守をしている時にロシア軍が南下を始めた。旅順に行ったのだが、そこから戻ってきた児玉は冴えなかった。
沙河戦が始まった。ロシア軍の南下運動に対して、日本軍は防御せず攻撃に出た。
日本軍の騎兵は、二個旅団が活躍している。一つは秋山好古の旅団で、最左翼を守っている。もう一つは最右翼で守っており、閑院宮載仁親王が指揮していた。この沙河戦での功績は大きかった。
この会戦における日本の死傷は約二万五百人にのぼった。約二個師団がまるまる消滅したかっこうだ。ロシアの損害は日本軍の数倍になる。全損害は六万人以上に上った。だが、ロシア軍は豊富な補給力によって充分な回復力を持っている。
沙河戦は一応の終息を見せ、以後「沙河の対陣」が始まる。冬が近づき、両軍とも冬営せざるをえない。
旅順の死闘はつづいている。第二回に続いて、総攻撃を繰り返したが、惨憺たる失敗に終わった。死傷はすでに二万数千人という驚異的な数字にのぼっている。
乃木軍司令部だけは二〇三高地の重要性を認めない姿勢は変わっていなかった。さらに参謀長の伊地知幸介は、度重なる作戦上の失敗を自分の方針の失敗であるとは思わず、大本営の責任にしていた。大本営が思うように砲弾を送らないからだというのだ。
旅順の日本軍が悪戦苦闘している頃、日本国家が恐怖しつづけたバルチック艦隊が本国を出港していた。
参謀本部は第七師団を旅順へやることにした。これで日本は空である。
旅順では、数え方によっては四次となる第三次総攻撃が行われた。この第三次総攻撃ほど、戦史上愚劣な作戦計画はなかった。
それに、乃木軍はかならず総攻撃を二十六日に行っていた。これはロシア側にも日本の大本営側にも不思議であった。わざわざ敵に準備させ、無用に兵を殺すだけのことでしかない。
本書について
目次
黄塵
遼陽
旅順
沙河
旅順総攻撃
関連地図
登場人物
秋山信三郎好古…兄
秋山淳五郎真之…弟
大山巌…参謀総長
児玉源太郎…参謀次長
井口省吾…少将
松川敏胤…大佐
黒木為楨…陸軍大将、第一軍
藤井茂太…参謀長
奥保鞏…第二軍
落合豊三郎…参謀長
梅沢道治…少将
閑院宮載仁親王…騎兵旅団長
大迫尚敏…中将、第七師団の師団長
乃木希典…第三軍
伊地知幸介…参謀長、少将
豊島陽蔵…砲兵部長、少将
東郷平八郎…中将、連合艦隊司令長官
島村速雄…連合艦隊参謀長、のちに元帥
上村彦之丞…第二艦隊
長岡外史…参謀本部次長
明石元二郎…大佐
有坂成章…少将、大砲の技術者
高橋是清
深井英五
ヤコブ・シフ…ユダヤ人金融家
ニコライ二世…ロシア皇帝
ウィッテ…ロシアの重臣
ベゾブラゾフ…ロシアの重臣
アレクセーエフ…関東州総督
ウィトゲフト…旅順艦隊司令長官
クロパトキン
ベリチコフ
ミシチェンコ…コサック騎兵集団の長
シタケリベルグ…中将
ロジェストウェンスキー…中将、バルチック艦隊司令長官