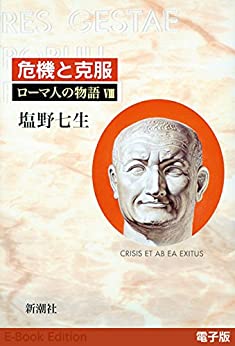覚書/感想/コメント
本書で書かれているのは二十九年間分。皇帝ネロの死からはじまって、トライアヌスが登場するまでの期間である。この間に就いた皇帝はガルバ、オトー、ヴィテリウス、ヴェスパシアヌス、ティトゥス、ドミティアヌス、ネルヴァの七人である。
この七人の中で知っている皇帝は、五賢帝に数えられるネルヴァ、それとかすかに記憶の中にありそうなのが、ヴェスパシアヌスと息子のドミティアヌスくらいである。だが、それも名前だけで、事績は全く知らない。
塩野七生氏は、この一連の物語を、学者の書くローマ史ではなく、作家の書くローマ史であると述べている。そして、自身はアマチュアにすぎないので、一つの「計器」を設けて書くことにしたと述べている。
学者は史料を信ずる傾向が強いが、作家は史料を頭からは信じない。それは歴史記述といっても人間が書き残したものであるから、書いた人間のバイアスがかかること、そして、考古学上の成果も発掘された物に限るという。
歴史記述を信じないというのは、いかにも作家らしい発言である。作家であるからこそ、書かれたものの中には主観性が入り込み、客観性を排除できない欠点があることを知っているのである。
そこで氏が設けたけ「計器」は、タキトゥスをはじめとする歴史家の評価よりも、その皇帝に続く後の皇帝たちが、彼の行った政策ないし事業を継承したか、それともしなかったか、というものだった。
この「計器」に基づくと、従来評価されてこなかった皇帝も評価の見直しを迫られることになるようだ。
面白い方法論だと思うし、客観性を確保できるやり方である。そして、歴史のストリームというのもつかむのに適していると思う。
客観性を排除できないことは分かりつつも、この時代を書く上で欠かせないのがタキトゥスの「同時代史」である。
タキトゥスは同著でこの時代を、苦悩と悲嘆に埋め尽くされた時代と評し、これが後世の評価を決定したらしい。そして、この後に続く「五賢帝」というのも、タキトゥス史観の影響力の強さを示している。
塩野氏は言う。確かに五賢帝はその器量の持ち主ではあったが、この前後の皇帝たちは皆悪帝もしくは愚帝だったのか?それならば、なぜローマ帝国はもっと早く崩壊しなかったのか?五賢帝による八十三年の統治期間で、その前後の四百二十年を持ちこたえることは絶対にできない。
それに、と続く。ローマ人は建国以来幾度となく襲ってきた危機を克服して興隆を果たした。タキトゥスがいうほどの絶望的な時代ではないのだ。この時代よりもさらに危機的な時代というのをローマは何度もくぐり抜けている。
それでも、興隆途上の危機と克服はさらなる繁栄につながったが、衰退期に入ると危機は克服できても繁栄にはつながらなくなる。
この危機は克服すれど、繁栄せずということへの追求こそがローマ帝国滅亡の要因に迫ることではないのかと氏は考えている。
歴史家ギボンは、ローマがなぜあれほども長く存続できたのかを問うべきである、といった。多民族、多宗教、多文化という国家としてはまとまりにくい帝国であったにもかかわらず、あれほどの長寿を保った理由である。
これへの解答なら簡単だと塩野氏はいう。ローマ人が他民族を「支配」するのではなく、他民族までローマ人、つまり「ローマ化」してしまったからである。大英帝国の衰退は各植民地の独立によるが、ローマ帝国は各属州の独立ないし離反は最後の最後まで起こっていない。
一つには、ローマ人の寛容性があるのだろう。ローマ人の「寛容」とは、信仰の自由は認める、生活習慣も認める、だが、それはローマ帝国に反攻しないかぎりにおいてである。
だが、これだけではないはずで、ローマ式支配の方法論というのは、現在においても考察の対象になりうるだろう。
そしてもう一つ。
ローマにはいわゆる官庁街がなかった。つまり独立した官僚組織がなかったということなのだが、なぜ独立した官僚組織をもたないで大帝国の運営ができたのか。今後の研究と考古学上の成果が待たれる。
この研究の結果により、ローマの体制というものがより明確になれば、現在にも転用できる部分というのはあるのではないだろうか?
このシリーズの一つの目的には「なぜローマが滅んだか?」というものがある。
通常、日本の学校で教えるローマの滅亡は蛮族の侵入が原因であるという印象を与える。だが、完全な誤解である。
ローマ全史は蛮族の侵入の歴史でもある。首都ローマまで侵入された紀元前三九〇年から、再び蹂躙される紀元後四一〇年までローマが持ちこたえたのは、防衛力が健在であったからである。
大移動と呼ばれる紀元五世紀の蛮族の侵入に際しても、東ローマ帝国は崩壊を免れている。防衛システムが機能していたからである。そのころ、西ローマの防衛システムは機能しなくなっていた。西ローマの防衛システムが機能しなくなって崩壊したのは、結果論である。
では、なぜ西ローマの防衛システムが機能しなくなったのか? そして、そうに至ったのはなぜか?それこそがローマの滅亡の最大の要因であると思う。この部分はこれからの「物語」のなかで語られていくのだろう。
第一章 皇帝ガルバ
(在位、紀元六八年六月十八日~六九年一月十五日)
ネロを排除すればローマ帝国の統治は支障なく続くと思っていた元老院と市民だったが、事態はそれほど簡単ではなかった。そもそもガルバはアウグストゥスの「血」に代わりうる別の権威の創出が必要だったから問題はより深刻だった。
ガルバは事態の深刻さを認識しておらず、急遽ローマに向かって皇帝の地位を確実にすべきだったを、のろのろとしていた。元老院が認めた「正当性」を過大評価しすぎており、名門の生まれという自負、七十二歳という高齢が必要な果断さを失わせたのかもしれない。
タキトゥスはガルバを一言で片づけている。「要するに平凡な出来の人物であった。」
協力者の人選も誤った。オトーを選ぶべきだったところをヴィニウスを選んだ。総督時代のガルバの指揮下にいた人物だ。これで支持者になり得た人々の支持を失う。さらに、このヴィニウスは私欲を満足させることしか知らない人物だった。
ガルバは財政再建策でも誤りを犯す。
結局、ガルバ体制の本格的なスタートを切ったその日に、ライン河沿いのローマ兵が反ガルバの態度を明確にする。
第二章 皇帝オトー
(在位、紀元六九年一月十五日~四月十五日)
新皇帝オトーはガルバの蒔いた種をつみとる羽目となる。ライン河沿いのゲルマニア軍団はヴィテリウスの擁立をしていたからである。
オトーの父親は「ティベリウス門下」の一員であった。ネロとは気があったらしいが、地方に飛ばされてから以前の彼を知る人達が驚嘆するくらい生活を変え、優秀な行政官に一変した。
平穏な時代なら、上出来な統治者であり得ただろうが、オトーの不幸は皇帝としての政治の前に「ゲルマニア軍団」対策に専念しなければならなかったことである。南下するゲルマニア軍団は十万。
救いだったのは、ドナウ河防衛の七個軍団がオトーへの指示をしたことであった。オトーはドナウ軍団が到着するまで持ちこたえる必要があった。そして「第一次ベドリアクム戦」がはじまる。
第三章 皇帝ヴィテリウス
(在位、紀元六九年四月十六日~十二月二十日)
ヴィテリウスは内戦では絶対に忘れてはならない敗軍の兵士たちの処遇を誤った。とくに中堅以下の兵士たちへの処遇は致命的なものだった。
これに対して「ドナウ軍団」は皇帝推挙の打診をムキアヌスにする。だが、ムキアヌスは皇帝支持がヴェスパシアヌスに向かうように努めた。
ムキアヌスは帝国の再建には既成の支配階級に属する自分よりも、外側にいるヴェスパシアヌスが適していると判断した。そして、ユダヤ人のエジプト長官アレクサンドロスも同じ判断をしていた。
こうして六十歳のヴェスパシアヌスをかつぎ、ムキアヌス、アレクサンドロス、ヴェスパシアヌスの息子ティトゥスの四人による明確な役割分担のもと行動が開始される。
「ドナウ軍団」が我慢しきれずにローマを目指してしまう。復讐の思いが彼らを駆りたてた。そして復讐の理由を与えた「ライン軍団」との激突がはじまる。「第二次ベドリアクム戦」である。
そして、ヴィテリウスは退位することで事態の収束を図ろうとしたが、失敗に終わる。
第四章 帝国の辺境では
カエサルとポンペイウスの間で行われた内戦のとき、属州明は蜂起しなかった。だが、皇帝が三人も入れ替わる六十九年のときには反乱が起きた。この無秩序状態を元に戻すのは皇帝ヴェスパシアヌスとその右腕ムキアヌスの仕事となる。
ブリタニアでも反乱が起き、ドナウ河防衛線ではダキア族がローマ領内になだれ込んだ。
深刻なのはライン河防衛線だ。ライン河防衛線では非主戦力とされた補助兵が主戦力の軍団兵を攻めるという前代未聞の不祥事が起きていた。
補助兵はゲルマン系であり、ライン河東岸に住む同じゲルマン系部族と呼応して行動し、さらにはガリア人にも呼びかけ、ガリア帝国を建設してローマの支配から独立しようとする動きまで見せる。ライン河の補助兵はバタヴィ族であった。
結局この反乱で、ライン軍団を構成していた七個の軍団の内、六個軍団までがゲルマン系の属州兵に屈することになる。
もう一つ、東方でもイェルサレムにおけるユダヤ戦役がある。後世の研究者は、ローマ帝国とユダヤ民族の対決という視点に重きを置き、ユダヤ戦役への注目度が高い。
だが、タキトゥスはガリア帝国事件の方を重く見ていた。
なぜなら、ユダヤ戦役の行方が帝国の安全保障に与える影響は間接的だったが、ガリア帝国の行方如何は直接的な影響を与えるからである。
第五章 皇帝ヴェスパシアヌス
(在位、紀元六九年十二月二十一日~七九年六月二十四日)
ヴェスパシアヌスは元老院に第一人者の承認を受けたにもかかわらず、それから十ヶ月も帰国を延ばした。その間、ヴェスパシアヌスはイェルサレムの陥落の報告をエジプトで待った。エジプトは小麦の供給源だ。いわばヴェスパシアヌスは「食を物質」にしていたのだ。
ヴェスパシアヌスがイタリアを留守にしている間にはムキアヌスが万事滞りなく諸政策を行っていた。万端の用意が調った上でイタリアへ帰国したのだ
ヴェスパシアヌスは「健全な常識人」だった。帝国の再建にはアウグストゥスのような超一級の政治力を必要としない。責務感が確固としていれば、遂行可能なのだ。
だが、ヴェスパシアヌスは新参者である。皇帝の権力のもろさをネロの一件で分かっていたヴェスパシアヌスは皇帝権力の強化に乗り出す。そして、元老院は皇帝を弾劾裁判によって、不適格者として「国家の敵」とすることができなくなった。
ヴェスパシアヌスは財政再建の面で最も有名で、最適の国税長官とさえ評されている。彼は税率を上げないで、また新税も課さないで、どうやれば税収を増やせるかを考え、成功させたのだ。彼と息子のティトゥスが行ったのは国勢調査だった。
なお、ヴェスパシアヌスが手がけ始めた物として、コロッセウムがある。
第六章 皇帝ティトゥス
(在位、紀元七九年六月二十四日~八一年九月十三日)
三十九歳で皇帝に就いたティトゥスの治世は度重なる大災害で彩られ、大事故の善後処置に没頭していうるうちに命の火を燃やし尽くしてしまう。享年四十。わずか二年の治世だった。
この大災害とは、ヴェスヴィオ山噴火、ローマの大火、イタリア全土への疫病発生だった。
ヴェスヴィオ山噴火によりポンペイが埋まった。このポンペイを襲った不幸は現在でこそその遺跡により有名となっているが、歴史上の重要度は低い。だが、作者は日本でいうところの小プリウスからタキトゥスへ送った二通の手紙を紹介し、様子を描いている。
第七章 皇帝ドミティアヌス
(在位、紀元八一年九月十四日~九六年九月十八日)
ローマ帝国には直訳するすると「記録抹殺刑」という刑罰があった。死後の名声を気にしたローマのエリートにとってはこれほど不名誉な刑罰はなかった。
この刑に処せられた皇帝にはネロがおり、カリグラも事実上この処遇を受けた。五賢帝のハドリアヌスもこの刑に処せられそうになっていた。ドミティアヌスも死後にしろこの刑を受ける。
ドミティアヌスがこの「記録抹殺刑」に処せられるほどのことをしたとは思えない。元老院による報復措置だったのではないか。
ドミティアヌスはヴェスパシアヌスの二男である。兄・ティトゥスの予期せぬ死により三十歳で皇帝となった。統治に必要な実務経験もなく、軍事上の経験もまったくない状態での登位だった。
早い時期の公共事業として、ドミティアヌス競技場の建設、コロッセウムの完成、ネルヴァのフォルムの三つを手がけている。
そして、最大の物が、ローマの防衛体制を語る上では欠くことを許されない、「リメス・ゲルマニクス(ゲルマニア防壁)」の建設である。このために、兵士への待遇改善と、ゲルマン人問題の解決が求められた。
ゲルマニア防壁は後の皇帝、特にトライアヌスとハドリアヌスが重視し、熱心に補強をする。完璧な物になるのはハドリアヌスの時代である。
だが、当時、前線に行くことのなかった元老院はその重要性を理解できず、批判の対象とした。
ドミティアヌスの時代は財政再建に苦労する必要がなかった。それはヴェスパシアヌスが財政を建て直してくれたためであった。
第八章 皇帝ネルヴァ
(在位、紀元九六年九月十九日~九八年一月二十七日)
ネルヴァからはじまる五人の皇帝を後代で五賢帝時代と呼ぶ。だが、だれがネルヴァを皇帝に推したか分かっていない。ただ、年齢的なものと、中道的な立場にあることから反発もなかったようだ。つまり、最初からショート・リリーフであることを予測された皇帝だった。
後継者の選択はネルヴァ自身が行ったようだ。皇位継承者が予想外の人だったからである。
養子に迎えるというかたちで指名されたのは、マルクス・ウルピウス・トライアヌスである。イベリア半島出身の属州出身者だ。
一年四ヶ月の治世の後、ネルヴァは死んだ。
本書について
塩野七生
ローマ人の物語8
危機と克服
新潮文庫 計約六五〇頁
目次
はじめに
第一章 皇帝ガルバ
(在位、紀元六八年六月十八日~六九年一月十五日)
ネロの死が、ローマ人に突きつけた問題/人心掌握の策/協力者人事/ヴィテリウス、皇帝に名乗りをあげる/ガルバ殺害
第二章 皇帝オトー
(在位、紀元六九年一月十五日~四月十五日)
人間オトー/「ライン軍団」対「ドナウ軍団」/武力衝突に向けて/大河ポー/「第一次ベドリアクム戦」/オトー自死
第三章 皇帝ヴィテリウス
(在位、紀元六九年四月十六日~十二月二十日)
敗者の処遇/シリア総督ムキアヌス/エジプト長官アレクサンドロス/ヴェスパシアヌス、皇帝に名乗りをあげる/本国イタリアでは/帝国の東方では/「ドナウ軍団」/「第二次ベドリアクム戦」/ヴィテリウス殺害
第四章 帝国の辺境では
属州兵の反乱/ユリウス・キヴィリス/攻めこまれるローマ兵/「ガリア帝国」/ローマ史はじまって以来の恥辱/反攻はじまる/勝利と寛容/「ライン軍団」再編成/ユダヤ問題/反乱勃発/ユダヤ人ヨセフス/ユダヤ戦役/予言/戦役中断/戦役再開/イェルサレム落城
第五章 皇帝ヴェスパシアヌス
(在位、紀元六九年十二月二十一日~七九年六月二十四日)
ローマへの道/帝国の再建/人間ヴェスパシアヌス/「皇帝法」/後継者問題/元老院対策/人材登用/「騎士階級」と平民への対策/ユダヤの王女/コロッセウム/財政再建/「パンとサーカス」/教育と医療/財源を求めて/死
第六章 皇帝ティトゥス
(在位、紀元七九年六月二十四日~八一年九月十三日)
ポンペイ/現場証人/第一の手紙/第二の手紙/陣頭指揮/死
第七章 皇帝ドミティアヌス
(在位、紀元八一年九月十四日~九六年九月十八日)
「記録抹殺刑」/人間ドミティアヌス/ローマの皇帝とは/公共事業(一)/給料値上げ/「ゲルマニア防壁」/カッティ族/内閣/司法/地方自治/公共事業(二)/ナイター開催/ブリタニア/ダキア戦役/反ドミティアヌスの動き/幸運の女神/平和協定/一つの「計器」/教育カリキュラム/恐怖政治/「デラトール」/「終身財務官」/暗殺
第八章 皇帝ネルヴァ
(在位、紀元九六年九月十九日~九八年一月二十七日)
ショート・リリーフ/トライアヌス登場/ローマの人事
〔付記〕
一ローマ詩人の生と死
年表
参考文献
フラヴィウス朝略系図/帝政初期皇帝一覧