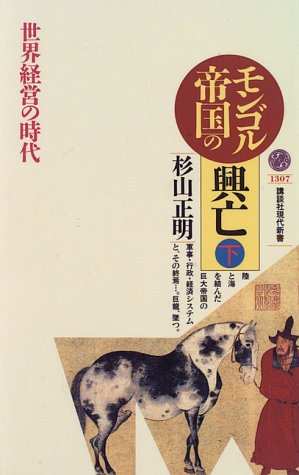世界史を高校で習ったなら、その習ったことやイメージの修正を迫られる内容でしょう。教科書よりも、本書の方が説得力を持つ記述が多いです。
十三世紀というのはモンゴルの時代ですが、そのモンゴルは短期間で消滅したというイメージがあります。
チンギス・カンを初代として、オゴデイ、グユク、モンケと続いたあと、帝国としてのモンゴルは解体し、クビライを初代とする中華王朝としての元が後を継いだというイメージです。
他には西北のキプチャク・カン国、西アジアのイル・カン国、中央アジアのチャガタイ・カン国という国々が、それぞれ完全独立したという風にあるといった感じでしょうか。
ですが、この完全独立していたというイメージは間違いで、それぞれが繋がりを持ったモンゴル帝国の一員として認識しなければ行けないことを本書を読むことによって気づかされます。
本書を読むことによって気づかされることの最も大きなことは、モンゴル帝国によってはじめて東西世界がつながったという事実です。
従来からも東西世界はつながっていたという見解があるようですが、組織だって運営されたというのはこの時代が初めてと考えた方が良さそうです。
このことによって、世界的にどのようなことが起きたのかというのは、重要な意味合いを持ちそうであり、今後の研究というのが待たれます。
おそらくは世界史の認識を根本的に変える必要が出てくるだろうと思います。
さて、モンゴルというとチンギス・カンでしょう。
このチンギス・カンに関する歴史研究を書く上で基本資料となるのは漢文の「元史」、モンゴル語を漢字で表記した「元朝秘史」、ペルシア語の「集史」です。
これまではこのうちの一つもしくは二つに基づいて書かれてきました。
しかし、本来はこの三つの史料を使って書かれなければなりません。
この三つ使ってのチンギス・カンの著作を書こうとすると、最低限、漢文・モンゴル文・ペルシア文を自在に読みこなせなければなりません。
その上で厳密に読み込んで、それぞれの差違を確かめるなどの基本作業が行われる必要がありますが、これまでのところなされていません。
そのため、いままでの歴史研究に関しては、その研究者たちのすぐれた個性による見解・感想・評論・物語の領域をでないのだそうです。
ようするに、言語の壁が大きく立ちはだかっているということのようなのです。
確かに言語体系の異なる三つの言語を自在に操れる歴史家というのはいないでしょう。一人の天才を待っている研究分野といえます。
教科書で習ったにも関わらず、その実在性が否定される、もしくは疑わしいという出来事は多いようです。
世界史を勉強したことがあるなら、「ワールシュタットの戦い」は聞いたことがあるはずですが、この会戦自体あったのか定かでないそうです。
また、ロシア帝国というのが俗称のキプチャク・カン国、本来はジョチ・ウルスと呼ばれるところから誕生したというのも、そうだったっけ?と思うかもしれません。
教科書というのは、所詮その程度のものということです。
「カン」「カアン」「ハーン」などの君称の混同がもたらした結果が、従来の誤った「四ハーン国の分裂」説のもととなったようです。
一般には「ハーン」で統一しがちですが、そうするとモンゴル皇帝と他の王侯との厳然たる違いを無視することになり、「フビライ・ハーン」と「フレグ・ハーン」と同列で並べるというナンセンスな状態になります。用語の使い分けの難しさを証明しているいい例です。
また、この様に用語の単位で混同が起きるというのは、史料が多言語に渡っているというのも影響しているのかもしれません。
最も重要とされる「集史」のイスタンブル本、それに準じる他の写本群との照合、二〇カ国語を超える膨大・多様なモンゴル時代関連の多言語文献との突き合わせと反復検証をしなければならない研究というのもいかにもしんどそうです。
(どうでもいいことですが、本書に対して反証したい人がいるとしたら大変です。上記と同じことを行ってからでないと、反証できないからです。反証するためには、最低でも同じ土台に立っていないと意味がありませんので…。)
こうした大変さを考えると、漢文の「元史」を中心とした漢文史料に、モンゴル語を漢字で表記した「元朝秘史」を加えて済ましたくなるのもわからないではないですが、この研究分野は新しい方向に進み始めているようで、こうした安直な方法では誤魔化しきれなくなってきているようです。
本書が執筆された1996年当時、漢文史料、ペルシア語史料を双璧とする多言語文献の壁を乗り越えて、時代全体を推し眺めようとする動きが出ているそうです。
モンゴル時代史の研究は世界中でかなり古い伝統と蓄積を持つ分野ですが、日本では新しい潮流が起りつつあるということで、この当時からどれくらい研究が進んでいるのでしょうか。
少なくとも、本書の出版当時にして、これまで考えられてきたモンゴル帝国とその時代の見解とは随分違った結論が生まれてきているそうです。本書を読めば明かです。
そうした成果をなるべく取り込んでコンパクトに伝えようとしたのが本書です。専門論文でも言及されていない事実の叙述もあり、叙述に関しての文献の呈示などはなされていませんが、結論だけを先取りする形で書かれているのだといいます。
裏付けのあるものを読みたい人は、本書以後に出版された専門書や論文を読まれるといいでしょう。
興味深かったのは二点ほどです。
一つ目は、「タラス会盟」が創作だったということです。イメージ化のもとは、「モンゴル人の歴史」の著者であるドーソンであり、その後の人がペルシア語の原典史料に直接当たらずに「タラス・クリルタイ」を当然の前提として解釈したために起きたことだそうです。
二つ目はモンゴル帝国の地図。「経世大典輿地図」に明示されものは、一三二九年以後の情況を示すものでしかないにもかかわらず、後世の学者は、あたかもその形がずっと前からあると誤解して、モンゴル帝国に関するズレを生み出したのだそうです。
こうした点は、現在の高校世界史の教科書などには反映されているのでしょうか?
内容
トルコのイスタンブールのトプカプ宮殿にモンゴル帝国の研究において最も根本となり最古・最良の古写本がある。ラシード・アッディーンの「集史」だ。ペルシア語で書かれた人類史上最大の歴史書である。モンゴル政権のフレグ・ウルス、俗称イル・カン国でつくられた。
「集史」がなければ、モンゴル帝国はおろか、中央アジアに展開したトルコ・モンゴル系の遊牧民たちの歴史も再構築が難しくなる。
有名な所として「百万の書」(俗称「東方見聞録」)がある。マルコ・ポーロという人物が見聞したとされるものだ。だが、実在性に疑問がある。
マルコ・ポーロは一人とは限らない。マルコ・ポーロは「集史」や「元史」をはじめとする「まともな」歴史文献の中には全くその名が見えないのだが、その元となる体験や知見をもつ人間が単数か複数いたことはまちがいない。
現在われわれが手にするそれは、研究者が各写本を継ぎ当てしてつくりあげた校訂本でしかない。
十九世紀から二十世紀にかけ、ロシアにバルトリドという偉大な歴史家が現われた。彼の研究によって、中央アジア・内陸アジアの世界の歴史が見事に浮かび上がってきた。加えて、それまであまり関係がないとされてきた、内陸世界と西アジア・中東・インド・西北ユーラシアの文明圏の歴史が密接に結びついていることがわかってきた。
十三世紀から十四世紀の後半までの間、世界の中心にいたモンゴル時代に、世界の歩みは根本から変わった。
モンゴルを中心にユーラシア世界は史上初めて緩やかに東西に広く結びついた。
十二世紀にユーラシアは東西の風通しがよくなった。そして十三世紀の初め、チンギス・カンに率いられたモンゴルがほとんど突如に浮上してくる。
チンギス・カンは族長の傍流という程度の家柄であり、その生涯に関しては確かな著述というのはない。史料があまりにも虚実が入り交じっているため、どこまでが史実なのかがわからないからである。
史料となるのは漢文の「元史」、モンゴル語を漢字で表記した「元朝秘史」、ペルシア語の「集史」、ほかにいくつかの文献があるが、それらが噛み合わない。
確実にいえるのは、確かな姿を現すのが、諸史料ほぼ一致して西暦一二〇三年の秋に、モンゴル高原の東半分の覇者となってからである。
モンゴルは優秀な戦闘力を持つ戦士群と、政略などに富む各種の文明人たちが結びついた集団だった。
チンギスの語義は諸説有り、よくわからない。
チンギスは牧民の組織化にとりかかり、東西合わせて六個の一族王家の真ん中にチンギスと末子トルイがいるふうにした。チンギスに直属する千戸群は西にボオルチュ、東にムカリをおく形となり、これがモンゴル・ウルスの全ての原型となる。
国家の名は「大モンゴル国(イェケ・モンゴル・ウルス)」であった。
チンギスは金国遠征から帰還すると、ただちに西方のホラズム・シャー国への遠征に取りかかる。
ホラズム・シャー国の君主はアッラー・アッディーン・ムハンマド二世。チンギスに巡り会う不運がなければ、イス
ラム史上に大きな足跡を残す可能性のあった人物だった。
従来、このホラズム・シャー国への遠征は、チンギス派遣の通商団が殺されたことへの報復だとされてきた。だが、誤解である。このことが起きる前からの既定の行動だったのだ。
また、この時大量の虐殺が行われたとされるが、もともとそんな大人口はいないので、桁が一つどころか二つくらい多い数字となっている。それに、モンゴルも大虐殺・大破壊を誇大に宣伝することによって、戦わずに降伏させる恐怖の戦略を意図していた。
仮に大虐殺・大破壊があったなら、衰退するはずの中央アジアは、モンゴル到来後も繁栄をつづけた。
チンギス没後、二年間はトルイが国権を代行したが、クリルタイが開かれ、全会一致でオゴデイが第二代の大カアンに選ばれた。
しかし、本当は疑わしい。
ともかく、オゴデイが一二二九年、新帝となる。
金国作戦を完璧に近い勝利で乗り切った。この時の英雄はトルイだったが、帰還する途中で不可解な急死を遂げる。
奇妙な美談が作られ、トルイとオゴデイに関わる東西史書の叙述はあまりにも不自然となっている。
これ以後十年間は、オゴデイを中心に、東方にオッチギン、西方にチャガタイという一種のトロイカ体制が続く。
カラ・コルムが帝国支配の中心となり、各種の機構も出来上がった。書記局兼財務庁は現在の感覚からは大きくずれたもので、地位と立場は低かった。
見かけとのズレがはなはだしいのが耶律楚材で、無力に近かった。そのため、「集史」をはじめとするペルシア語の史書に現われない。
西方遠征にはジョチの次子でジョチ一門の当主となっていたバトゥが任命された。この軍にはオゴデイ家のグユクやトルイ家のモンケもメンバーになっていた。補佐したのは四匹の犬の一人、スベエデイであった。王子たちはチンギスの孫の世代に移っていた。
遠征軍の主力は少年部隊であった。十代の前半であることが多く、遠征の課程ですぐれた大人の戦士になっていった。
バトゥらは当時ルースィと呼ばれていたロシアに向かった。
ルースィは多くの諸公国に分れていた。このためモンゴルに対抗できず完敗した。「タタルのくびき」の開始である。
だが、これは訂正を必要とする。多くの都市は無傷であり、ルースィの壊滅という常識は疑問が多い。モンゴル側の恐怖の宣伝もあるためである。また、アレクサンドル・ネフスキーの存在と活動は、ルースィが壊滅していなかった何よりの証拠となっている。
「タタルのくびき」は実のところ「ルースィ諸公のくびき」でもあった。
モンゴル軍はさらに西へ進み、「レグニツァの戦い」もしくは「ワールシュタットの戦い」が起きる。
だが、世界史上有名なこの会戦も、本当にあったのか定かでない。同時代の文献には全く見えず、十五世紀の文献で突然大きく語られるからである。だから、あったとしても、ささやかなものであった可能性が高い。
バトゥのもとにオゴデイ崩御の知らせが届き、モンゴル諸王家の部隊は東方へ引き上げてゆく。だが、バトゥのジョチ家はヴォルガ下流の草原に腰を据え動かなくなった。
「ジョチ・ウルス」はトルコ系のキプチャク族が大半を占める独特の構成となり、そのため俗称としてのキプチャク・カン国という風にいわれる。
西北ユーラシアに巨大な世界が誕生し、ゆるみ、崩れ、変形しながらも三百年続き、ロシア帝国もこの中から誕生した。
オゴデイが死に、跡目はチンギスの孫の世代に移っていった。
グユクの即位をめぐっては、大きな禍根を遺した。グユクの即位がなかなか実現しなかったのは、もともとの無理に加えて、バトゥが強硬に反対しつづけたことにある。
だが、グユクは二年足らずで突然死に、帝位は再び空となる。
後を継いだのはバトゥの力添えも得たモンケであった。識見・能力にあふれ、実力・実績・名望・血筋のどれをとっても文句のない人物であった。
そのモンケは即位そうそうにおそるべき専制君主であることを見せつけた。ゆるみきった帝国の統制を果断、極端に回復させた。
モンケは実弟クビライに東方を委任させる。三番目の実弟フレグにイランの地から西方全てを委任させることにした。
この当時、西欧では十字軍の時代。教皇はインノケンティウス四世だった。「モンゴルの恐怖」が最も高まった時代だからこそ、教皇の権力は輝いた。
グユクから教皇に宛てた返書というのがある。これに関しては未解決の点が多い。
また、これまでモンゴル語の印の刻文やトルコ語による冒頭の言葉を根拠にして「王権神授」の思想をもっていたと言われがちであったが、モンゴルの素朴な「上天」崇拝をヨーロッパで言う「王権神授思想」といえるのかは疑問である。
ヨーロッパにおいて、最も正確で有益な報告はフランチェスコ会の修道士ギョーム・ドゥ・ルブルクの「旅行記」である。だが、この存在が知られるようになったのは近年であり、長い間故意に存在が伏せられていた可能性さえある。
モンケ政権の誕生で歴史に浮上してきたのは、モンケの実弟クビライ、フレグ、アリク・ブケであった。クビライもフレグも、ほとんど謎に包まれた前半生から一二五一年に突如登場する。
モンケが突如死に、一二五九年から一二六〇年は世界史上で稀に見るスケールの激動の年となる。
クビライは軍事力を得て、自派のみのクリルタイを開き、大カアンとなる。四十六歳である。一方で、アリク・ブケも新帝となり、ここに二人の大カアンが並び立つことになる。
正当性で言うなら、アリク・ブケの方が真の大カアンである。「集史」においても、アリク・ブケを歴代皇帝の一人として扱っている。アリク・ブケが大カアンであったことは間違いなく、クビライの軍門に下るまでの足かけ五年間は、皇帝であった。
だが、帝位はモンゴル史上初めて武力による争奪となった。四年間にわたる帝位継承戦争が起る。最初からクビライ有利であった。
これまでは、この帝位継承戦争で、モンゴル本地派と漢地派、もしくは遊牧派と定着派の争いとする見解がとられてきたが、戦争の結果誕生した大元ウルスを「中華王朝」とする固定観にひきずられて、決めつけたものであり、事実とは遠い強引な憶断でしかない。
そもそも、クビライ陣営は遊牧戦闘力において勝っていた。
フレグの西征の目的はイスマーイール派とバグダードの両勢力の討滅、イランの平定とされるが、その割りには大がかりな準備と手配りであった。別の解釈もあり、フレグ・ウルスの形成そのものにあったというものがあり、「集史」の記述を典拠としている。
イスマーイール派を覆滅させたあと、モンゴルの進撃はすばやかった。バグダードは陥落し、三十七代五百年にわたるアッバース朝が滅びた。
モンゴルはシーア派とスンナ派の核となる存在を、わずか二年のあいだに消滅させ、イスラームと中東の歴史に大きな転換を与えた。
バグダード陥落の際、八十万の住民が虐殺されたという話も、モンゴルの「無敵の神話」と「恐怖の戦略」の一環による宣伝だった。なぜなら、最盛期のバグダードでもそれほどの人はいなかった。
バトゥの西征の時もそうだが、国を挙げての大遠征の場合、モンゴルは行ける所まで行こうとしている。
フレグ本隊もモンケ他界という突発事により北シリアからやむなく旋回したのであり、先鋒部隊は東地中海沿岸を目指していた。
モンゴル帝国は東のクビライ政権、西のフレグ・ウルスという権力の核を生み出し、帝国自体も、中身と性格を大きく変化せざるを得ない時代に突入してゆく。
一二六四年。帝国の紛乱は収まりを見せ、帝国には五つの政治勢力の塊が存在した。東北には東方三王家、モンゴル本土と華北にクビライ、中央アジアにチャガタイ家、西北ユーラシアにジョチ家、西アジアにフレグ・ウルスである。
だが、この中で帝国の西三家の当主が相次いで一年以内に急死するという、恐ろしいまでの偶然が重なる。
そのため、中央アジアが再び動乱に包まれていく。
モンゴルは単純な「恐怖の時代」の終焉を迎え、多極化の時代に入ろうとしていた。そして、時代は軍事から政治、通商への転換をはじめようとしていた。
クビライ以後のモンゴルの権力は建前と現実の二重構造となる。帝国は巨大になりすぎ、一族ウルスのうち、ジョチ・ウルス、フレグ・ウルスなどはそれ自体が帝国と呼んでも指しつかえない規模となっていた。
西暦一二六〇年、クーデタ即位をしたクビライは四六歳だった。この時から一二九四年に八〇歳で死ぬまで現役の帝王でありつづけた。
クビライの新国家は、国家・社会・経済が一つのシステムとして統合されるものとなる。
また、クビライ政権は国家プロジェクトを一斉に実施に移していった際、当初から海上への視野をもっていたらしい。海と陸をジョイントする考えがあったということだ。
クビライは首都をカラ・コルムから上都(開平府をあらためた)へ移し、中都をもう一つの都とする。
成年に達していた息子たちを副王として起用し、三大王国を基本骨格として二小王国を加えた構造となる。
一二六六年末。クビライは中都郊外に巨大帝都の造営を号令する。発令の時から「大都」と名付けられた町は、現在の北京である。
新しい国号として「大元大モンゴル国」が正式名称となる。略して大元ウルスである。
大元の名は「易経」の「大いなる哉、乾元」から採った。乾元とは天、宇宙を意味し、それはモンゴルでいう所の「テングリ」である。
「大元」を中華王朝の伝統に基づくものとするのは、誤解といわざるを得ない。
チャガタイ家のアルグの死により中央アジアは再び混乱に陥った。一二六六年クビライはチャガタイ家の傍流バラクを送り込んだが、このバラクはクビライの意に反して、中央アジアで公然とチャガタイ領への拡大を開始する。
一二六九年にタラス河ほとりで会盟がおこなわれた。集まったのはバラクの他、オゴデイ家のカイドゥ、ジョチ家のモンケ・テムルの代理人。
「タラス会盟」と呼ばれるもので、これまではカイドゥがクビライに対抗する大カアンに選出され、モンゴル帝国は二大陣営に分裂したとされてきたが、この「定説」は史料に何の根拠もない「創作」である。
イメージ化のもとは、「モンゴル人の歴史」の著者であるドーソンであり、その後の人がペルシア語の原典史料に直接当たらずに「タラス・クリルタイ」を当然の前提として解釈したために起きたことである。
実際の会盟では、協議が多岐にわたったようである。もっとも利点があったのはカイドゥだったのではないかと考えている。
カイドゥは帝位継承戦争の初めから反クビライの巨頭とされがちだが、カイドゥが中央アジアの覇者になるのは、下って一二七〇年代の後半以後でしかない。
史料を離れた過大なイメージ化や単純化によってそう考えられてしまったのだ。
バラクはカイドゥにすすめられるまま、西方の覇王を夢想した。そして「カラ・スゥ平原の戦い」が起きる。この戦いはバラクとアバガだけでなく、モンゴル帝国全体の行方を左右する決戦となり、モンゴル同士としては史上屈指の規模の会戦となる。
バラクは大敗戦し急死を遂げる。ペルシア語の史書「ヴァッサーフ史」はカイドゥの暗殺と明言している。
帝国を見ると、クビライの押さえる東半、西北のジョチ・ウルス、西南のフレグ・ウルスという枠組みは固定する。間の中央アジアだけがぐちゃぐちゃの状態に戻り、タラス会盟は意味を喪失する。
中央アジアはカイドゥが率いるオゴデイ一門と、ドゥア率いるチャガタイ一門という図式が成立し、それなりの安定を取り戻す。
これまでの「カイドゥ大カアン説」はもとより、「オゴデイ・カン国」とか「チャガタイ・カン国」とう考えや、両「カン国」のクビライへの抵抗という「通説」は現実から遊離した誤解といわなければならない。
一二八〇年の前後を境にして、シリギの乱などもあり、チャガタイ家とオゴデイ家、中央アジアもはっきりとした一線を画することになる。
クビライは帝位継承戦争の中で漢人大軍閥の反乱にあい、華北軍閥たちの地付き状態を解消することにする。世襲の土着軍閥はいなくなり、「定説」では封建土着諸侯の割拠状態から伝統中華王朝の州県制度を基礎とした中央集権体制へ大変身を遂げたということになるが、漢文史料の字句の表面だけを見た安直な見解といわざるを得ない。
クビライは南宋作戦のためにモンゴル騎兵をほとんど使わないことにした。クビライの新国家は軍事までもがハイブリッド状態だった。政権側が意図してつくりだしたのだ。
戦争からは個の力や偶然の要素を排除しようとし、システム化した。物量と計画と統制で、勝つべくして勝った。
南宋は一挙に劣勢となり、打つ手なく消滅の日を迎える。
南宋を接収したモンゴルは海に出た。江南という富を取り込み、海上ルートも掌握して、超高域のモンゴル圏をつくりだそうと、あらかじめ計画した。
陸上を舞台とするイラン系ムスリム商業勢力に、ムスリム海商たちとも連絡を図った。
日本に関連して、従来、書状が傲岸無礼で日本を恫喝する内容だったから日本の頑なな姿勢は仕方がなかったといわれてきたが、書状は冒頭を初めとして驚くほど低姿勢だった。
冒頭の「上天眷命」はクビライ政権が使う定型句の「とこしえの天(テングリ)の力にて」の漢訳雅文版でしかなく、さて、とか、のぶれば、と同じ置字に類する。
一〇〇万を超す職業軍人である旧南宋軍をどうするかはクビライ政権にとって頭の痛い問題であった。そこでランクわけをして、弱兵たちを海外進攻に向けた。
第二回日本遠征の江南軍がそうであり、彼らが携帯したのは武器ではなく農機具であったらしい。つまり、大部分は入植のための移民に近かった。
襲来前と襲来の間も、日本の貿易船は大陸と往来をしていた。襲来後は、たいへんな経済・文化交流の波が起り、明治に至るまでこれほどの交流は見られなかった。
「通説」でいう「東南アジア侵略の失敗」にもかかわらず、一二九三年前後には南シナ海、ジャワ海、インド洋を結ぶ洋上ルートがモンゴルの勢力圏内に入っていた証拠がある。
そして、海上については「伝統アジア交易システム」といわれてきたが、そこにはモンゴルとの関わりを認めたくないという心理が濃厚に漂っている。他に「前期世界システム」という用語があるが、東西大交流がモンゴルとクビライにより出現したことは否定しようがない。
一二七六年。中央アジアを制圧していたノムガンの大元ウルス軍が一瞬のうちに瓦解した。シリギの乱は三年ほどで沈静化したが、中央アジアの大元ウルス軍による直接支配は永遠に消え失せた。
カイドゥが再び大きく浮上する。カイドゥの下に三つのウルスが集まり、当時のペルシア語の史書がいう「マムラカト・イ・カイドゥーイー(カイドゥの国)」ができあがる。
シリギの乱より一〇年ほど後、東方三王家でナヤンの乱が起きる。カイドゥが応じ、東西からの挟み撃ちの形になる。クビライ政権最大の危機である。
七三歳になっていたクビライは自ら迎撃を決意し、「ナヤン・カダアンの乱」は終わる。
クビライが八〇歳でなくなり、後継にはテムルがついた。漢語では成宗、モンゴル語のおくり名はオルジェイトゥ・カアン(幸いもてるカアン)である。
クビライ他界により、カイドゥに身を寄せていた者達は離れていき、カイドゥに衝撃を与える。カイドゥはそれまでの方針を放棄し、乾坤一擲の勝負に出ることになる。
大元ウルス軍の陣容がカイドゥ側を圧倒し、カイドゥは一三〇一年他界する。これにより、大元ウルスは、クビライがいなくても揺るぎない国家・政権であることが疑いなくなった。中央アジアも大元ウルス体制に回帰し、一三〇五年には東西は完全に和合した。
中央アジアでは大カアンの権威のもと、ドゥア一族をいただくチャガタイ家の単独主権が確立する。「チャガタイ・ウルス」の成立である。
一三〇七年成宗テムルが没した。後継問題が懸念されており、実権は筆頭皇后のバヤウト族のブルガン・カトンが掌握していた。実権者の地位を失いたくない彼女は奥の手を使ったが、カイシャンが後を継いだ。
カイシャンは全モンゴルの支持を受けた大カアンであった。内陸ルートによる政治の壁は払拭され、東西交通は民間レベルでも政権レベルでも活発化した。
なかでも重要なのは、カイシャンの登極を機に、キプチャク、アス、カンクリなどの諸族からなる特殊親衛軍団が浮上したことである。
一三一一年カイシャンは前触れなく没した。不可解な死であり、カイシャンの葬儀や新帝選出のクリルタイも招集されず、閣僚たちが処刑され中央首脳部が壊滅する。アユルバルワダが大カアンとなるが、明らかにクーデタであった。政権を奪われた者達の、恨み頃による産物に相違なかった。
本当の権力者は実母の皇太后ダギであった。漢文史料では仁宗アユルバルワダと英宗シディバラの治世を、漢文化人が優遇された良い時代としているが、それは表面にすぎない。
国家の基盤は緩み、仁宗・英宗の時代に、西方の三大ウルスは正式の使節団は送ってこなかった。
クビライの国家システムは農産物からの税収ではなく、重商主義の財政運営といえるものだった。最大の収入源は、専売品とされた塩の引換券の売上代金である「塩引」であった。塩とリンクした有価証券である。
これにモンゴルが基幹通貨とする銀とをリンクさせた。銀は当時の通貨需要に対しては多くなく、塩引はまたとない補助通貨となる。
この塩引に次ぐ収入は、商取引から徴収する「商税」であった。間接税に当たる。
大カアンは決して生まれながらの絶対専制君主であったわけではなく、職分を遂行するかぎりにおいて絶対無比の権限を付与される。大カアン個人が私身において揮える権力は、ささやかなものにすぎなく、これまで往々にして誤解がある。
また大カアンの交代は王朝の交代と変わらなかった。
モンゴルは在地支配に対する関心が薄かった。宗教にたいして平等で寛容だといわれるが、寛容性は無関心の言い換えであり、モンゴルは異様なほど軍事と政治、支配と統治だけに関心があった。宗教も技術も思想も情報も統治の手段にすぎなかった。
また、モンゴル政治の特徴として目立つのは宴会政治という面である。
大カアンの無力化とモンゴル中央政権の空洞化は覆いがたい趨勢となり、上都と大都の両京内戦、チャガタイ軍の大東進とコシラの挫折、といった全体をひっくるめて「天暦の内乱」と呼ばれるものが起きる。
これ以後、中央政局は諸族親衛隊軍団が掌握し、大カアンは彼らの傀儡となる。
新しいモンゴルの境域区分は「経世大典輿地図」にも明示されたが、これは一三二九年以後の情況を示すものでしかない。
モンゴル権力の揺らぎは西の三大ウルスでも起きる。
一三六八年朱元璋により大都が占領される。これをもって中国史では元朝滅亡というが、実際はこれ以後二〇年ほど一種の南北朝状態となる。
モンゴルは依然としてありし日のチンギス帝国ほどの勢力圏と影響力を保持していたのだ。
やがて、モンゴルの統合力が徐々に薄らぎ、一四世紀後半に次第にフェードアウトしていく。
ポスト・モンゴル時代に、モンゴルほどではないが、以前ではあり得なかったような大帝国が一斉に出現する。東西南北に四つの単位の帝国が長期に並び立つことになる。
東の明帝国、一七世紀半ばからは大清帝国。西ではオスマン帝国。南ではティムール帝国が一六世紀、インドまで南下してムガル朝と呼ばれる帝国をつくる。北ではロシア帝国が浮上する。
明は大元ウルスにとっては出来の悪い相続人だった。クビライ時代以後に芽生え、出現したものの多くを台無しにした。明朝はひどく後ろ向きの存在だった。
殺伐とした気風に満ちた陰惨な時代で、実態は暗黒帝国といってもよかった。また明は海上進出・海洋発展を国家としては放棄した。日本では日明貿易が有名であるが、日元貿易の方が盛んであった。
明朝・清朝はモンゴルによって巨大化した中華を前提とし、多種族複合の共生社会という点で踏襲している。明を漢族による民族国家とするのは、日本において目立つ顕著な誤解である。
モンゴル帝国の西半にいたモンゴルについて、解体後はるばる東の故郷へ帰還したとされる説も、かつてはあったが、そんな事実はない。そのままその地の住民となったのだ。
本書について
モンゴル帝国の興亡
杉山正明
講談社現代新書
解説書
目次
序 歴史を語るものたち
トプカプの「集史」 コロンブスの夢 バルトリド生涯の挑戦 時代という名のなにか
Ⅰ 時代の被造物モンゴル
1 モンゴル・ウルスの誕生
夜明け前 闇に包まれた高原 年老いた蒼き狼 チンギスに求められたもの 淳朴な牧民と心悪しき隣人 モンゴル・ウルスの形 第一次対金戦争 西へ! オアシスの太陽ホラズム・シャー モンゴルは「破壊」しなかった? 草の匂いがする帝国
2 世界征服への道
怪しい後継者選び 注目の第二次対金戦争 人口圧作戦 つくられた美談 邪魔者を消した三頭体制 草原のメトロポリス 書記局の実態 中央と属領 華北再編 世界戦略 モンゴル軍少年部隊 最初の大失敗 クチュの南征 ルースィの大地 バトゥの西征 東方からの嵐 巨大なジョチ・ウルス
3 帝国の動揺
混迷する跡目 老雄オッチギンの野望 ドレゲネの賭け キング・メーカー 有能すぎる悲劇 第二次世界征服計画
4 ヨーロッパとの出会い
プレスター・ジョン伝説 憧れと恐怖の東方 マシュー・パリスの証言 巨人インノケンティウス四世 幸運な人カルピニ グユクの返書 不幸な使節団 聖王ルイの挫折 ルブルクの旅
Ⅱ 世界史の変貌
1 クビライの奪権
クビライとフレグ 激動の年 確執 モンケの急逝 後継の資格 運命の賭け 長江のほとり 皇帝アリク・ブケ 負の遺産 チャガタイ家の反乱 クーデタ政権
2 フレグの旋回
西征の狙い イランとその彼方 暗殺教団 アルボルズの雪 バグダード陥落 運命の旋回 未完の遠征 アイン・ジャールートの惨敗
3 多極化時代の幕開け
査問 幻の統一クリルタイ 帝国と世界の行方 変貌の時
モンゴル帝国史年表(一一五五~一二六六)
索引
Ⅲ 陸と海の巨大帝国
1 世界の改造者
帝国の二重構造化 巨大すぎることの負担 老人皇帝クビライ 大統合のプラン 夏冬の巡業首都圏 クビライ王朝の三大・二小王国 世界の帝都 海と陸への起点 大いなるテングリの国
2 草原のゆらめき
風雲児バラク タラス会盟の実像 オゴデイ家の復権 会盟の意味 バラクの夢 アバガの罠 混迷する中央アジア 新たなる図式
3 大河の国へ
郝経の雁書 李璮の「反乱」 事変の波紋 変わる華北 南宋作戦の方針 襄樊包囲作戦 戦争のシステム化 西から来た新兵器 呂文煥の選択 大進攻 南宋接収
4 海上発展の道程
海の時代へ 半島の悲劇 クビライと倎 モンゴルによる「王政復古」 過剰な「国書」解釈 第一回日本遠征の意味 第二回日本遠征の真相 蒙古襲来余波 ユーラシア大交易圏
Ⅳ ゆるやかな大統合
1 内陸争乱から東西和合へ
第一の揺り戻し ナヤンの挙兵 クビライ最後の出陣 カイドゥのあせり 史上最大のモンゴル会戦 東西和合 ドゥアの中央アジア簒奪 「皇太后」ブルガンの策動 カイシャンの奪権 「パクス・モンゴリカ」の到来 王朝に兆す翳
2 帝国の経済システム
企業家たちの群れ 「オルトク」が結ぶユーラシア大交易圏 銀がめぐり、世界は回る 意外な文書中心行政 大カアンによる「大統領制」 宴会政治
Ⅴ 解体とその後
1 天暦の内乱
愚帝イスン・テムルの死 カイシャンの遺児たち 両京内戦 兄弟「中都」にせめぐ 失われる大統合
2 沈みゆくモンゴル世界
三大ウルスの揺らぎ 順帝トゴン・テムルの末世 江南決戦の覇者 落日
3 モンゴルの裔たち
アジアに遺された四つの帝国 暗黒の相続人「明」帝国 北へ帰ったモンゴルたち 清朝を生きたモンゴル 近現代の嵐 歴史という名のいとなみ
あとがき